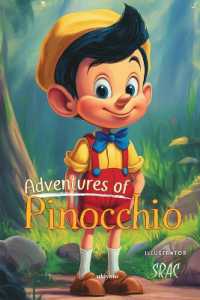出版社内容情報
ことばによるコミュニケーションでは推論の果たす役割が大きいという基本的な認識から始めて、表意と推意の区別、概念的意味と手続き的意味、記述的側面と解釈的側面を論じ、応用面について最新の動向を概観する。
"第1章 イントロダクション - コミュニケーション能力と解釈原則
1.1 コミュニケーションを可能にするもの
1.1.1 ことばとコミュニケーション/1.1.2 言語とメタ表示能力
1.2 関連性理論の研究対象と基礎概念
1.2.1 研究対象/1.2.2 発話解釈における効率性/1.2.3 関連性理論の基礎(修正推論モデル/関連性の認知原則と伝達原則/意図明示的刺激の処理装置)/1.2.4 発話解釈過程
第2章 表意(explicature)と推意(implicature)
2.1 発話によって伝達される2種類の意味
2.2 Grice(1967, 1975/89)のWhat is saidとWhat is implicated
2.3 関連性理論の表意と推意
2.3.1 表意(表意に貢献する4つの語用論的手段/言語的意味の不確定性/表意の明示性の程度/基本表意と高次表意)/2.3.2 推意(前提推意と帰結推意/推意の強さ)/2.3.3 表意と推意の相互作用と位置付け(相互調整/発話の認知処理に関わるレベル)/2.3.4 表意と推意の境界問題(and接続/「尺度含意」)
2.4 まとめ
第3章 概念的コード化と手続き的コード化
3.1 発話によって伝わる情報
3.1.1 発話によって伝わることと意図明示的伝達/3.1.2 言語的伝達と非言語的伝達/3.1.3 言語的伝達とコード化/3.1.4 概(4.3.3.1 疑似条件文の分析/4.3.3.2 メタ言語的否定の分析)
4.4 伝統的レトリックの再分析
4.4.1 メタファーの分析/4.4.2 メトニミーの分析/4.4.3 アイロニーの分析/4.4.4 ジョークなど笑いの分析(4.4.4.1 ジョークの分析/4.4.4.2 ユーモアの分析/4.4.4.3 パロデイーの分析/4.4.4.4 だじゃれの分析)/4.4.5 その他のレトリックの分析(4.4.5.1 ニックネーム の分析/4.4.5.2 同一表現の繰り返し(Repetition)の分析/4.4.5.3 控えめ表現(understatement)の分析/4.4.5.4 トートロジー(Tautology)の分析)
第5章 更なる複雑な言語使用の分野への応用
5.1 広告の分析
5.2 翻訳の分析
5.3 丁寧さ(politeness)など社会的要因の分析
5.3.1 社会的想定(social assumptions)について/5.3.2 What are you looking at? を侮辱として解釈する場合/5.3.3 交感関係の伝達(phatic communication)と関連性/5.3.4 ケーススタデイー: butと丁寧さの分析
5.4 言語障害の分析
5.5 おわりに
"
内容説明
本書は、人と人が行うコミュニケーションの発話の理解に焦点をあてる。発話の内容に関して、何が伝達されるのか、なぜそのような意味になるのか、どの部分が明示的に伝達され、どの部分が含意として非明示的に伝達されるのかといった側面である。この領域は、Griceによって先鞭がつけられたが、近年GriceとGrice派の分析方法の不備を明らかにし、新しい普遍的原則によって上記のような問題に答えようとする関連性理論が、有効かつ有望な分析方法として注目を集めている。関連性理論は、発話がいかに解釈されるかということに関する理論である。本書は、この理論によって明らかになった発話理解の諸側面を整理し、更なる発展の可能性を探ろうとするものである。
目次
第1章 イントロダクション―コミュニケーション能力と解釈原則(コミュニケーションを可能にするもの;関連性理論の研究対象と基礎概念)
第2章 表意と推意(発話によって伝達される2種類の意味;Grice(1967、1975、1989)の‘what is said’と‘what is implicated’ ほか)
第3章 概念的コード化と手続き的コード化(発話によって伝わる情報;概念的コード化 ほか)
第4章 言語の記述的用法と解釈的用法(ルース・トークに基づく伝達;解釈的類似性に基づく伝達 ほか)
第5章 より複雑な言語使用の分野への応用(広告の分析;翻訳の分析 ほか)
著者等紹介
東森勲[ヒガシモリイサオ]
1951年大阪府生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。現在、龍谷大学文学部教授
吉村あき子[ヨシムラアキコ]
1959年奈良県生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程(英語学専攻)単位取得退学(1993)。博士(文学)(大阪大学1997)。現在、奈良女子大学文学部助教授。著書に『否定極性現象』(英宝社、1999、市河賞受賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 松島かのん「今しか見られない」SPA!…
-
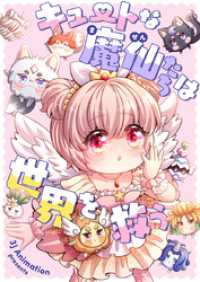
- 電子書籍
- キュートな魔仙たちは世界を救う【タテヨ…