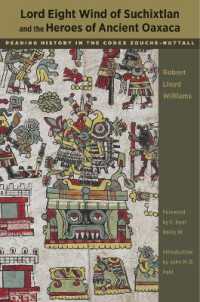出版社内容情報
原始に続き、仏教美術・やまと絵・水墨画を生んだ上中古、障屏画と浮世絵・南画・写生画を育てた桃山江戸、和と洋を生かした近現代。書・建築・工芸・茶道も含め世界観の中で捉える。
【目次】
序
Ⅰ 研究の方法
1 日本美術史の方法論―現状の整理と問題点
2 日本美術史における時代区分
Ⅱ 原始美術
1 古代の造形と美
Ⅲ 古代・中世の提起
1 仏教美術の立体的摂取と展開
2 仏教美術の平面的摂取と展開
3 仮名の成立と書
4 やまと絵の形成とその意味
5 絵巻物の展開
6 水墨画から墨絵へ
7 水墨画の展開
Ⅳ 近世の美術
1 室町から桃山へ
2 風俗画の表現意識―桃山から江戸へ
3 江戸期流派の興隆
4 浮世絵―発生と展開
Ⅴ 近代の美術
1 西洋の摂取
2 日本画と洋画
3 平面と立体―絵画・彫刻二分法の再考察
Ⅵ 建築・工芸と茶道
1 建築と庭園の日本的特質
2 意匠と思想―唐様と和様
3 くらしの美
4 芸道と美術
Ⅶ 在外研究
1 日本の仏教彫刻の1400年―海外からの視点
図版一覧
索引
内容説明
原始に続き仏教美術・やまと絵・水墨画を生んだ上中古、障屏画と浮世絵・南画・写生画を育てた桃山江戸、和と洋を生かした近現代。書・建築・工芸・茶道をも含め世界性の中で考える。
目次
1 研究の方法(日本美術史の方法論―現状の整理と問題点;日本美術史における時代区分)
2 原始美術(古代の造形と美)
3 古代・中世の提起(仏教美術の立体的摂取と展開;仏教美術の平面的摂取と展開;仮名の成立と書;やまと絵の形成とその意味;絵巻物の展開;水墨画から墨絵へ;水墨画の展開)
4 近世の美術(室町から桃山へ;風俗画の表現意識―桃山から江戸へ;江戸期流派の興隆;浮世絵―発生と展開)
5 近代の美術(西洋の摂取;日本画と洋画;平面と立体―絵画・彫刻二分法の再考察)
6 建築・工芸と茶道(建築と庭園の日本的特質;意匠と思想―唐様と和様;くらしの美;芸道と美術)
7 在外研究(日本仏教彫刻の1400年―海外からの視点)