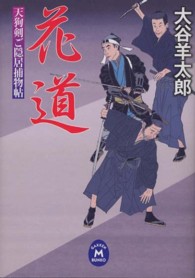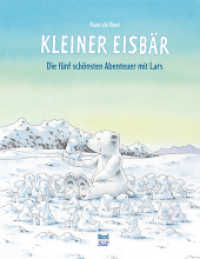内容説明
脱「モノ」化する世界の音楽実践、「ネットワーク・ミュージッキング」とは。音楽に対する欲望の変質を、社会と技術の相互作用を焦点に描き出す。音楽文化の現在に見取り図を示すシリーズ第3巻。
目次
序章 音楽文化の変容
第1章 音溝からパターンへ
第2章 音楽の象徴的支配
第3章 脱「モノ」化する世界
第4章 参照とキャッシュメモリ
第5章 利用可能性の“リスト”
第6章 音楽聴取における「いま・ここ」性
第7章 コミュニケーションが主導する音楽の流行現象
終章 「参照の時代」の新たな音楽実践
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
愛楊
2
2009年出版。博士論文がもとになっている。作品を所有することの呪術性は、ストリーミングサービスの時代においてはたとえばApple MusicのマイライブラリというUXによって擬似的に担保されているといえるし、作品に対する人間の現象的側面に関する議論には興味深いものがあった。ニコニコ動画では、〈同一〉なる複製ではなく、〈類似〉の複製が続いていくということや、親作品へのリスペクト性といった論点がゼロ年代後半に提出されていたことに驚く。2024/04/02
鳩羽
1
モノから情報、所有から参照への流れを、アナログ・デジタル録音の違いや、もっと時代を遡って音楽家とオトの関係から探っていく。音楽に限らず文章でもそうだが、インターネットの「あちら側」に大量の情報があり、それを随時参照できるなら所有や複製はいらないかもしれないと思った。何を持っているかが個性の現れだった時代から、何を参照したかの履歴が個性となる時代……って読書メーターこれがまさしくそうだった。2013/03/28
pddk
1
現状の音楽環境を考えるにあたって、メディアと情報流通の超絶変化を捉えなきゃだけど、そういう方向での第一歩!て感じですかね。これが何を意味するのか、という部分を考えていかなくては。2009/12/19
tegege
0
博士論文が元なだけに堅苦しい文章が続く。だが内容は非常に興味深い。所有から参照へ向かう、ネットならではの音楽聴取文化の変貌に考えをめぐらすためのヒントが、いくつも読み取れた。2013/04/06
新平
0
本書の初版が2009年8月、収められている文章が2005年から2008年まであるので個々の事象の分析に関しては2012年7月現在に読むにはややツラい部分も多いが、人々の音楽に対する接し方を参照という概念で括ったのはなるほどと思う。まあ、どっちかというと、「音楽も」と言ったところなのだが。2012/07/08