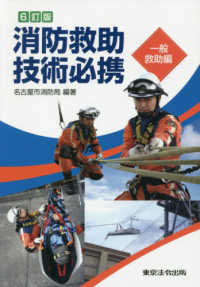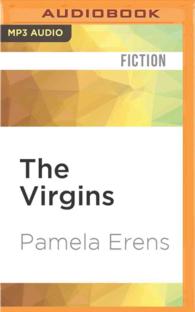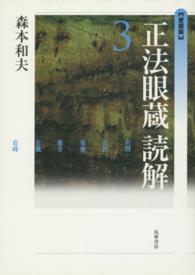出版社内容情報
日本におけるラップ・ミュージックの生産過程の分析を通じ、文化のグローバル化/ローカル化の過程と、定着した外来文化が独自の発展を遂げる、その動態を描写する。
アフリカ系アメリカ人というエスニック・マイノリティから誕生し、そのローカル性に強く規定された「ラップ」。この外来音楽文化は、どのようにして日本に流入・定着し、独自の市場と自律的価値をもつにいたったのか。「ラップ」の生産過程に着目し、グローバル化/ローカル化の過程で外来文化が独自文化に昇華されていく過程を克明に描く。
[関連書] 東谷護編著 『拡散する音楽文化をどうとらえるか』 (勁草書房刊)
序章 なぜラップに注目するのか
1 文化のグローバル化/ローカル化
2 なぜラップに注目するのか
3 日本のラップ
4 ラップの生産
5 本書の構成
第1章 ローカルなラップをいかにとらえるか
1 「ゲットー」から
2 ラップの日本への流入
3 ポピュラー音楽としてのラップ──文化的真正性と商業性
4 ローカルなラップの位置
第2章 ローカル化の欲望
1 サウンド──「日本らしい」音への志向
2 言語──日本語で「レペゼン」する
3 <イデオロギー>──実践の意味づけ
4 ローカル化の欲望の意味
第3章 ラップの自明化とローカルな実践
──あるラップ・グループの音楽実践を事例として
1 一九九〇年代後期以降
2 グループ結成
3 音楽的志向
4 練習、レコーディング
5 ライブ
6 「本場」の弱化とローカルな実践
第4章 ラップ実践と人的ネットワーク
──二つのグループの実践を事例として
1 ラップ実践と人的ネットワーク
2 風神
3 キカイダー
4 人的ネットワークとクラブ
5 ローカルなラップを媒介する人的ネットワーク
第5章 ラップとレコード産業
──レコード会社におけるラップの販売戦略を事例として
1 レコード産業と日本のラップ
2 ラップを手がける
3 アーティストの選別
4 専門誌、店頭における宣伝活動
5 ストリート・プロモーション、ストリート・マーケティング
6 ディストリビューション
7 ローカルなラップ市場
第6章 ローカルなラップを媒介する企業活動
──ラップ・イベントにおける企業スポンサーの事例から
1 企業スポンサーという販促活動
2 販促活動におけるヒップホップの位置
3 イベントの選別
4 イベント、ブレイクビーツにおけるスポンサー業務
5 ローカルなラップ実践を媒介する企業活動
終章 ラップの自律化・自明化、そしてその先
1 日本のラップにおける認識論的・実体論的ローカル性
2 自律化・自明化という傾向──ロックのローカル化過程を補助線として
3 「日本文化」は異種混淆的なのか
4 自律化・自明化と支配的個別性
5 グローバルな力学、新たなローカル化の契機
注 あとがき
参考文献
人名索引
事項索引
内容説明
音楽と聴衆の媒介作用“メディエーション”に焦点をあてるポピュラー音楽研究の新潮流。日本におけるラップ・ミュージックの生産過程分析を通じ、文化のグローバル化/ローカル化の過程と、定着した外来文化が独自の発展を遂げる動態を活写。音楽文化の現在に見取り図を示すシリーズ第2巻。
目次
序章 なぜラップに注目するのか
第1章 ローカルなラップをいかにとらえるか
第2章 ローカル化の欲望
第3章 ラップの自明化とローカルな実践―あるラップ・グループの音楽実践を事例として
第4章 ラップ実践と人的ネットワーク―二つのグループの実践を事例として
第5章 ラップとレコード産業―レコード会社におけるラップの販売戦略を事例として
第6章 ローカルなラップを媒介する企業活動―ラップ・イベントにおける企業スポンサーの事例から
終章 ラップの自律化・自明化、そしてその先
著者等紹介
木本玲一[キモトレイイチ]
1975年東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了。博士(学術)東京工業大学。現在、相模女子大学人間社会学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チェ・ブンブン
まれむりん
Jumpei Komura
マッキー
寺基千里