内容説明
自由であることの困難。就職、結婚、私たちの大切な選択を運まかせのギャンブルにしてしまわないために、いま社会にできることは何か。
目次
第1部 信頼にいたらない世界(自由は増え、信頼は失われる;自由は増え、アイデンティティは傷つく)
第2部 それでも信じることの意味(信頼の二つのタイプ;信頼の構造;信頼と民主主義)
著者等紹介
数土直紀[スドナオキ]
1965年メキシコに生まれる(神奈川県で育つ)。1995年東京大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。現在、学習院大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buuupuuu
21
社会が自由になっても、望んだように生きられるとは限らない。自由になるとは、不確定になるということでもあるからである。リスクにさらされることにより不安が増し、自己肯定感も毀損されてしまう。著者はこのことを、結婚と就職を例にとって説明している。不確実性に対処するには、社会的に自由を制限するか、リスクを広く分散する仕組みを作るかしなければならない。そして、私たちは自由な社会に生きているのだから、後者のやり方を採用するしかない。リスク分散的な仕組みが備わっている社会では、教育水準の上昇が、社会への信頼の鍵になる。2024/12/08
りょうみや
21
著者の本2冊目。前半が自分で自由に選べるが選ばれる立場でもある結婚と就職の具体的な話で、そこから自由の信頼性、やり直しのできる社会制度の話になっていく流れは面白い。数理社会学者らしく数式は使っていないがゲーム理論的な考え方がよく分かる。自由と信頼の関係と定義を改めて深く考えさせられる。2022/07/21
ぽん教授(非実在系)
4
自由が不自由を生むパラドックスの話から始めて山岸説を拡張して信頼ⅠとⅡに至るところまでは学説整理的な個所であり、実際に分析するところは応用編か。権威主義的な信頼Ⅰに対して信頼Ⅱが望ましいという命題自体は分かるが、昨今では大学や市民団体の狼藉がクローズアップされていて信頼が崩壊しているように見える中で、本書の結論部分は大いに変わってしまったのではないかとも感じる。2021/11/17
Toshi_S s2
4
自由が増すことで選択にともなう不確定な要素も増え、かえって自由の質が下がってしまうことが結婚と就職を例に議論されていて、それについてはイメージしやすかった。その後の信頼を主軸としたデータ分析は、議論自体は興味深かったが、抽象度の高い一般的な問題へと議論のレベルがシフトしていたため、前半で述べられていたトピックへのフィードバックがほしかった。リスクの分散や期待値にもとづく行動(選択)といったキーワードを結婚や就職に当てはめるとどんなことが言えるのか、そこをもう少し知りたかった。2015/04/09
偏頭痛
3
「自由でありさえすればいいのではない。どのように自由であるかが問題なのである。」自由を得たために不自由になっているなどそのように時代の変化で良くなっていると思われるものが本当に良くなっているのか?というのを改めて検証している内容。確かに選択が増えたからといって幸せになれてるいるのかといえば疑問ではある。しかしアンケートなどデータを元に証明をしようとしてるものの信頼など人の頭の中にしかないようなものでなかなか厳しいところもあったりという印象。2014/11/19
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】骨の髄まで私に尽くせ。【…
-

- 電子書籍
- 境界線のその先は。 ~ムカつく同期との…
-
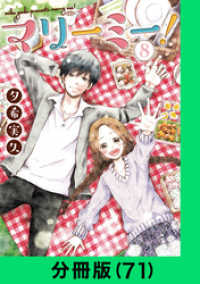
- 電子書籍
- マリーミー!【分冊版(71)】 LIN…
-
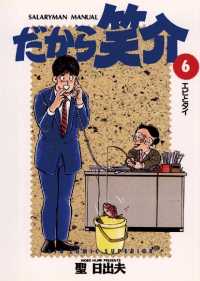
- 電子書籍
- だから笑介(6) ビッグコミックス





