出版社内容情報
信頼というテーマを倫理や実存主義の枠から解放し,社会的メカニズムとして考察する道を拓く。信頼の機能や形態,その形成や変容などを細かく分析する。ルーマン理論入門。
内容説明
人間の社会は〈世界の複雑性〉にどのような〈縮減メカニズム〉で対処しているのか。信頼を機能分析の土俵に乗せる。
目次
第1章 準拠問題―社会的な複雑性
第2章 存続と出来事
第3章 馴れ親しみと信頼
第4章 複雑性の縮減としての信頼
第5章 情報の過剰利用とサンクションの可能性
第6章 人格的な信頼
第7章 コミュニケーション・メディアとシステム信頼
第8章 戦術的な構想―チャンスならびに束縛としての信頼
第9章 信頼に対する信頼
第10章 信頼と不信
第11章 信頼への準備
第12章 信頼と不信の合理性
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hitotoseno
12
たとえば貨幣でもって商品を買おうとするとき、我々は商品が貨幣の価値に見合っているかどうかを知っているわけではない。というか、貨幣は所詮紙切れであって、千円札なら千円、1万円札なら1万円の価値があるか、と一度考え出してみるとかなり怪しい。それでも我々は商品には相応の価値があると見込んでそれを購入するし、貨幣には相応の価値があると見込んでそれを使う。マルクスは不安含みの経済において根本のところで行なわれている行為を「命がけの飛躍」と形容したが、ルーマンはそれを貨幣経済のみならず社会全体に適用しようとする。2017/10/31
roughfractus02
11
ランダムな分子同士がぶつかり合う世界では、混沌から秩序が生じるのは奇跡だろう。著者は個々人が行動選択を自由に行える世界で社会が成り立つとする場合、複雑性の縮減が起きていると想定し、従来の社会で「信頼」と呼ばれる機能がこれに当たるとした。複雑性を縮減する信頼について本書は、これまで通り行う「慣れ親しみ」、相手の人格に基づいて行為する「人格的信頼」、貨幣(経済)、権力(政治)、真理(科学)等のシステムが準拠する「システム信頼」を区別する。興味深いのは、機能分化と信頼の相互的関係が社会を自己産出するという点だ。2024/07/29
coaf
8
卒論のために購入したが、僕の興味とはずれていた。そのせいか、何を言っているかちんぷんかんぷんだった。理論社会学の論文は苦手だ。哲学書が読めるのに、どうして理論社会学は読めないのか。捉えどころの無さは似たようなもんだと思うんだけどなあ。目が文字の上を滑って行く時は大体文章の意味を理解できていない。各文の意味は理解できても、それを解釈、消化できていない。途中からは斜め読みした。2013/08/29
イリエ
6
「信頼」を機能から考察した書。貨幣や権力もあるが愛に関してはない。この本について語ることは私にはできないが、感想として、足元が崩れるような体験になった、とはいえる。空気より意識してこなかった関係性が、複雑性の縮減メカニズムで説明されるのは心地よい場合もあった。2018/07/26
ぷほは
3
再再読。一見すると存続と出来事や慣れ親しみと信頼という前半の現象学的用語群を土台にした、複雑性の縮減とシステム/環境、人格信頼とシステム信頼、信頼と不信といったシステム論的な議論として読めるが、行動科学や心理学の紛争解決論などに影響も受けている、らしい。この辺はそれぞれ文献を当たってみないと分からないが、中盤に出てくるコミュニケーションメディアや再帰性、システムが利用するバイナリーコードなどの議論が後期ルーマンへの助走に感じられた。パーソンズとの同時並行の論争から彫琢されていく過程としても読めるわけだ。2018/09/13
-
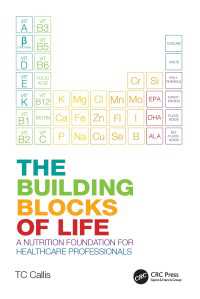
- 洋書電子書籍
-
生命を支える栄養の基礎
The …
-
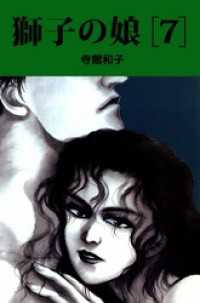
- 電子書籍
- 獅子の娘 7巻 まんがフリーク







