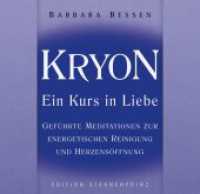出版社内容情報
「子育て支援労働」を実証分析するはじめての学術書。市民性・当事者性が強調される労働実態と社会経済的評価の重要性を示す。
少子化対策以降に制度化されてきた一時保育やひろば事業といった「地域子育て支援」。全国働き方調査データをもとに、活動に従事する人々の労働実態を明らかにする。地域の子育てを支えるものとして制度に位置づけられながら、アンペイドワークの延長線上にみなされるその労働の問題を、社会学や経済学の視点から問うはじめての学術書。
内容説明
「子育て支援」はケアワークである。地域の子育てを支えるものとして制度に位置づけられながら、アンペイドワークの延長線上にみなされるその労働の問題を、全国働き方調査データをもとにはじめて社会学や経済学の視点から問う。市民性・当事者性が強調される労働実態を実証分析、社会経済的評価の重要性を示す。
目次
「子育て支援労働」とは何か
第1部 制度的・歴史的文脈から子育て支援労働を考える(地域子育て支援労働の源泉―1990年代初頭まで;子育てする親が生成した子育て支援労働―非営利・協同セクターによる当事者活動の萌芽から制度化途上に;子育て支援労働の専門性を問う―ケア労働の分業化と再編の中で)
第2部 調査データの分析から考える(子育て支援者の労働時間・訓練機会・賃金―労働経済学からみた「地域子育て支援労働」;どのような支援者が無償労働に従事するのか―業務の種類と労働時間の関係に着目して;地域子育て支援の制度化と非現場ワークの増大;子育て支援労働は地域に何をもたらすのか?―ワーカーズ・コレクティブにおける経済的報酬と働くことの意味をめぐって;子育て支援労働者にとっての経済的自立の困難と可能性―ワーカーズ・コレクティブにおける経済的報酬と働くことの意味をめぐって)
第3部 子育て支援労働の課題(地域子育て支援労働の制度化―1990年代以降)
地域子育て支援労働研究のさらなる展開をめざして
著者等紹介
相馬直子[ソウマナオコ]
1973年生。2005年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。現在、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
松木洋人[マツキヒロト]
1978年生。2005年慶応義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得退学。現在、大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。