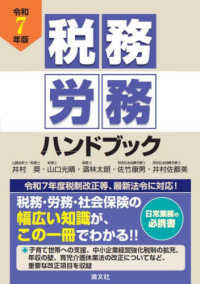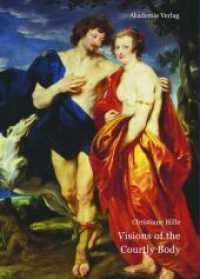出版社内容情報
植民地朝鮮の児童保護事業の展開を分析、養育に関する近代的知識が朝鮮に流入した過程と「産み育てること」の意味の変化を描き出す。
はしがき
図表等目次
凡例
序 章 本書は何を問うのか
第一節 「生」と「政」をめぐる問題
第二節 社会事業政策の変遷
第三節 二つの視座
第四節 本書の構成
第一章 医療宣教師によるソーシャルサービス
第一節 医療宣教の危機
第二節 伝道婦人の必要性──家庭訪問における役割
第三節 乳幼児死亡率問題化のプロセス
第四節 『嬰児養育』にみる新しい育児知識
小括
第二章 朝鮮総督府による乳幼児愛護運動──二つの転機
第一節 愛護運動のはじまり──「子宝」から「国宝」へ
第二節 朝鮮人の乳幼児死亡率の問題化とその解決策
第三節 デーから週間への拡大に伴う変化
第四節 二度目の転機──戦時の児童愛護週間
小括
第三章 朝鮮総督府済生院養育部の孤児養育──孤児たちの「ユートピア」?
第一節 孤児問題の多様性
第二節 農場移転前の養育システム
第三節 院外保育と院内保育の方針変化
第四節 農場における孤児養育
小括
第四章 朝鮮総督府永興学校の感化教育と「不良児」をめぐる言説
第一節 一九三〇年代初頭の社会事業と少年保護法制
第二節 永興学校の収容経緯
第三節 教科課程の変化
第四節 阿部虎之助による感化教育の方針と実践
第五節 永興学校訪問記にみる子どもの不良化に関する言説
小括
第五章 慶北救済会の活動展開と孤児養育の意味変化
第一節 「棄児都市」大邱府
第二節 嶺南共済会の発足と運営難
第三節 運営方針の転換
第四節 孤児の収容経緯
第五節 孤児養育の実際
小括
終 章 「生」と「政」の絡まるところ
第一節 本書を通して見えること
第二節 おわりに──総括と今後の課題
注
あとがき
初出一覧
巻末年表
参考文献
人名索引
事項索引
田中 友佳子[タナカ ユカコ]
著・文・その他
内容説明
宣教師、総督府、伝道婦人―啓蒙・統治・媒介を担う三者が錯綜、植民地政策の展開にともなう子育ての変容を描く。近代医学に基づく「正しい」子育てと子どもの選別。孤児院や感化院における「忠良勤勉なる農民」育成。「産み育てること」に生じた変化を、統治する側とされる側、両者を媒介した介在者の働きに着目し、植民地朝鮮に近代的養育が浸透していく過程を膨大な資料から描き出す。
目次
序章 本書は何を問うのか
第1章 医療宣教師によるソーシャルサービス
第2章 朝鮮総督府による乳幼児愛護運動―二つの転機
第3章 朝鮮総督府済生院養育部の孤児養育―孤児たちの「ユートピア」?
第4章 朝鮮総督府永興学校の感化教育と「不良児」をめぐる言説
第5章 慶北救済会の活動展開と孤児養育の意味変化
終章 「生」と「政」の絡まるところ
著者等紹介
田中友佳子[タナカユカコ]
1985年福岡県北九州市生まれ。津田塾大学学芸学部卒業。九州大学大学院人間環境学府博士後期課程単位修得退学。博士(教育学)。社会福祉士。韓国国際交流財団(Korea Foundation)Fellow、日本学術振興会特別研究員、九州大学人間環境学研究院助教を経て、九州大学大学院人間環境学研究院学術協力研究員、西南学院大学非常勤講師、北九州市立大学非常勤講師等。専攻は教育史、児童福祉史、教育福祉学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 仕事帰り、独身の美人上司に頼まれて【分…
-

- 電子書籍
- 昭和元禄落語心中 新装版(1)