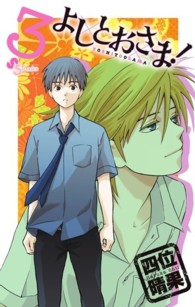内容説明
実証研究と理論研究はどのような関係にあるのか。構造化理論が提供する、実証研究を支える理論的フレームワーク。ギデンズの理論的主著、待望の邦訳!
目次
第1章 構造化理論の諸原理
第2章 意識、自己、社会的出会い
第3章 時間、空間、範域化
第4章 構造、システム、社会的再生産
第5章 変動、進化、権力
第6章 構造化理論、経験的調査、社会批判
著者等紹介
ギデンズ,アンソニー[ギデンズ,アンソニー] [Giddens,Anthony]
1938年生まれ、イギリスの社会学者。現在は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカルサイエンス(LSE)のEmeritus Professorであると同時に、労働党選出の貴族議員でもある。ハル大学、LSEに学び、1961年レスター大学講師に就任、1970年にはケンブリッジ大学へ移り、同時にキングス・カレッジのフェローとなる。1985年、新設されたFaculty of Social and Political Scienceの社会科学部門の教授に就任する
門田健一[カドタケンイチ]
早稲田大学非常勤講師(専攻は社会学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
25
1984年初出。社会学:先進社会、近代社会に照準を合わせた社会科学の一部門(5頁)。退化というか未開社会も文化人類学で分析できるけど。構造化理論の構造:社会的再生産に再帰的に関わる諸規則と諸資源(20頁)。極限状況:大多数の個人に影響を及ぼす予見不可能な徹底的断絶が生起する場面、制度化されたルーティンの確実性を脅かす、破壊する局面がある(90頁)。時間の管理:官僚制一般の特徴(187頁)。そのわりにサボっている人がいそうな組織文化ですが? 2015/05/05
SQT
5
個人的にはめちゃくちゃよかったです。特に6章の批判的注解のところ。「社会学的な」ということばを使う人がたまにいますが、その辺りをバッサリと切ってくれます。自分のテーマが境界横断的(もっとも、当然創られた、そして創られ続ける途上にある境界ですが)だったのでなおさら。ギデンズといえば「再帰的」「脱埋め込み」みたいな単語だけは聞いたことあるという人が多いと思いますが、その辺りのエッセンスや、由来が出てきて、かなり理解が捗り、かつ染み込むとおもいます。決定論に陥らず、主体を過大評価しすぎないというバランスが良い2017/05/12
ぷほは
2
ゼミ輪読にあたってしまったので、ささーっと再読。やはり突っ込んだところは分かりやすく、基本的なところは噛んで含めるように反復して説明されるので、馬鹿にされているような気分になり、かつケムに巻かれているような気分にもなるという、要するにあまり良い本ではないという感想は変わらず。例えばフーコーの批判に対してギンズブルグと違うというのは歴史学に通じてなくても常識なのでわざわざ書く必要ないと思うし、「フーコーの身体には顔がない」というのも議論として展開すれば面白くなりそうなのに言いっぱなしで終わっているのが残念。2018/11/04
萌
1
いままで読んだ本でいちばん難しかった... まったくわかっていない...けどギデンズの人柄が垣間見えるようでとてもおもしろかった2023/07/09
ぷほは
1
出たときに某先生が「あーあの読まなくていい本邦訳されたんだ」と言っていて、いやでもそうは言っても構造化理論有名だしと読んでみると、思った以上に読まなくていい本だった。別に書かれてある内容が下らないわけではなく、網羅性のために独創性が犠牲になってるだけで、且つ日本語で読めるレビュー論文で書かれている以上のことがあるわけでもない、というだけのことだ。ここまでは別にディスってるわけではない。それより行為-構造-構造原理の循環性と超越性の両立が、客体化-外在化-内在化の現象学的社会学モデルと区別し難いのがどうも。2016/09/15