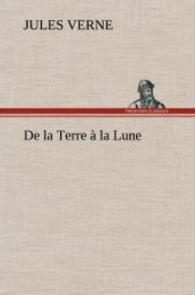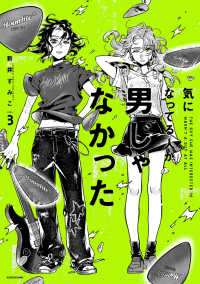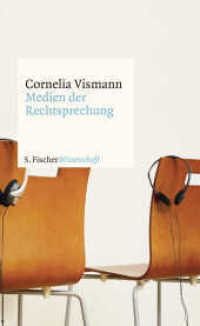出版社内容情報
ジェンダー理論の達成をふまえ、歴史的資料を縦横に駆使し、法と歴史学・社会学の学際的架橋をめざす。意欲的、刺激的な試み!
第1部「ジェンダー秩序と法」で方法論的・歴史的枠組を示し、第2部「近代的ジェンダー・バイアスの生成」でヨーロッパ近代秩序としての「公私二元構成」の問題点に、姦淫罪、嬰児殺、読書協会を例に鋭く切り込み、第3部「法秩序のなかの家族と生殖」で「親密圏」への国家と法の関与を指摘する。
関連書:田端泰子・上野千鶴子・服部早苗編『ジェンダーと女性』(共著、早大出版部)
──第1部 「ジェンダー秩序」と法秩序──
第1章 「ジェンダー研究」の展開と「ジェンダー法学」の成立
第1節 「ジェンダー法史学」の意義と目的
第2節 「ジェンダー法学」の成立と「ジェンダー法史学」
第2章 「ジェンダー秩序」の2類型
第1節 「ジェンダー秩序」の類型化仮説
第2節 「キリスト教的=身分制社会型」ジェンダー秩序と
「公私二元的=市民社会型」ジェンダー秩序
──第2部 近代的ジェンダー・バイアスの生成──
第3章 ヨーロッパ近代の公私二元構成
第1節 「公」と「私」──概念の変遷
第2節 「公/私」関係の歴史と展望
第4章 「法と道徳の分離」にみるジェンダー・バイアス──姦淫罪とその廃止
第1節 「風俗犯罪」と姦淫罪
第2節 近世バイエルンの姦淫罪
第3節 姦淫罪の廃止と「性の二重基準」の確立
第5章 「人道主義」のジェンダー・バイアス──嬰児殺論をめぐって
第1節 嬰児殺論の位相
第2節 啓蒙期の嬰児殺言説
第3節 「人道主義」の勝利とジェンダー
第6章 「公共圏」のジェンダー・バイアス──啓蒙期の読書協会
第1節 「公共圏」としての啓蒙空間
第2節 男たちの「公共圏」
第3節 コミュニケーションのジェンダー・バイアス
──第3部 法秩序のなかの家族と生殖──
第7章 法秩序としての「近代家族」
第1節 近代家族法システム
第2節 「近代家族」論争と近代的家父長制
第8章 「逸脱者」としての「未婚の母」と「婚外子」
第1節 婚外子法制の現状
第2節 前近代ヨーロッパにおける婚外子法制の展開
第3節 「未婚の母」の変化──啓蒙期法典編纂
第4節 19世紀前半のプロイセン婚外子法改革とジェンダー
第9章 「家族の保護」と「子の保護」の競合──ワイマール~ナチス期の婚外子法改革論
第1節 ドイツ民法典婚外子法
第2節 ワイマール~ナチス期の婚外子法改革論
第10章 生殖管理のジェンダー・バイアス──ナチス優生政策と断種法
第1節 ナチス優生学の歴史的位相
第2節 ナチス優生法制の背景と比較
第3節 ナチス断種法の手続と実態
主要文献目録
あとがき
索引
内容説明
ヨーロッパ近代秩序としての公私二元構成―その生成過程には、ジェンダー・バイアスの生成が伴った。姦淫罪(法と道徳の分離)、嬰児殺(人道主義)、読書協会(市民的公共圏の成立)の3側面から立証。
目次
第1部 「ジェンダー秩序」と法秩序(「ジェンダー研究」の展開と「ジェンダー法学」の成立;「ジェンダー秩序」の2類型)
第2部 近代的ジェンダー・バイアスの生成(ヨーロッパ近代の公私二元構成;「法と道徳の分離」にみるジェンダー・バイアス―姦淫罪とその廃止;「人道主義」のジェンダー・バイアス―嬰児殺論をめぐって ほか)
第3部 法秩序のなかの家族と生殖(法秩序としての「近代家族」;「逸脱者」としての「未婚の母」と「婚外子」;「家族の保護」と「子の保護」の競合―ワイマール~ナチス期の婚外子法改革論 ほか)
著者等紹介
三成美保[ミツナリミホ]
1956年香川県生れ。1988年大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学。摂南大学法学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。