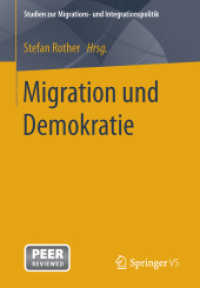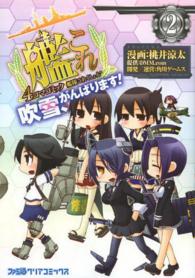出版社内容情報
温暖化対策をどのように進めていくか、そのために現実の環境政策を産業政策・雇用政策とどのように組み合わせていくか、望ましいポリシー・ミックスを提言していく。
京都議定書の第一約束期間が迫るなか、持続可能な経済成長を目指して環境政策を推進する上で、日本が約束している温室効果ガスの削減戦略が問われているところである。本書は、ポスト京都議定書に向けた新たな地球温暖化防止の枠組み作りのための議論が活発化する現在、環境保全と経済成長の両立のためのポリシー・ミックスを提言する。
はじめに
序 章 …………………………………………………土居信彦・長谷川裕一
0.1 はじめに
0.2 地球温暖化の現状
0.3 世界的な取り組み
0.4 わが国政府の取り組み
0.5 地方の取り組み
0.6 民間セクターの取り組み
0.7 まとめに代えて
第1章 温室効果ガス排出削減と経済成長………………………大沼あゆみ
1.1 はじめに
1.2 伝統的な経済成長と環境保全のとらえ方と環境クズネッツ曲線
1.3 効率的な環境利用とは
1.4 炭素原単位からみる経済成長と環境保全
1.5 炭素原単位からみた京都議定書の影響
―短期的観点からの成長と環境保全―
1.6 ポスト京都における削減義務と均等な負担
1.7 炭素原単位を減らす手段:炭素税と排出権取引
1.8 環境税の炭素排出量に与える効果
1.9 環境税収の使途と経済成長
1.10 排出権取引と経済成長
1.11 おわりに
第2章 エコロジカル経済学の背景と意義…………………………倉阪秀史
2.1 エコロジカル経済学とは
2.2 エコロジカル経済学の背景
2.3 エコロジカル経済学の基本的な枠組み
2.4 生態系サービスの持続可能性
2.5 人工資本と環境負荷
2.6 人的資本と社会資本
2.7 エコロジカル経済学と政策
第3章 環境政策の経済的評価………………………………………栗山浩一
3.1 はじめに
3.2 環境政策と環境評価手法
3.3 環境政策の評価事例
3.4 おわりに
第4章 環境税制改革とポリシー・ミックスの経済評価………………諸富徹
―イギリスとドイツを事例として―
4.1 はじめに
4.2 イギリスの環境税制改革とポリシー・ミックス
4.3 ドイツ環境税制改革の定量評価
4.4 おわりに
第5章 欧州諸国のエネルギー関連税と環境税の比較制度分析……林希一郎
5.1 はじめに
5.2 欧州主要国の温暖化対策に関連する税制
5.3 欧州諸国の温暖化対策のための税制の比較
5.4 おわりに
第6章 温暖化対策の国内制度設計…………………………………西條辰義
―上流比例還元型排出権取引制度―
6.1 はじめに
6.2 背景と提案の概要
6.3 上流比例還元型排出権取引制度
6.4 おわりに
第7章 温暖化ガスの排出権取引制度の政策効果………………山本隆三
―アメリカとEUの排出権取引制度の実績から―
7.1 はじめに
7.2 京都議定書と京都メカニズム
7.3 アメリカの排出権取引制度
7.4 EUでの温暖化ガスの排出権取引制度
7.5 温暖化ガスの排出権取引制度の問題点
7.6 温暖化問題への取り組み
第8章 環境対策における差別的対応………………………松本茂・横山彰
8.1 はじめに
8.2 環境対策の差別的対応の事例
8.3 現状の温暖化対策
8.4 差別的環境規制を利用する場合の問題点
8.5 おわりに
索 引
内容説明
今日本が問われている温室効果ガスの削減を産業政策・雇用政策とどのように組み合わせていくか。持続可能な経済成長を目指しながら、ポスト京都議定書に向けた新たな地球温暖化防止の枠組み作りを実現する政策を提言する。
目次
第1章 温室効果ガス排出削減と経済成長
第2章 エコロジカル経済学の背景と意義
第3章 環境政策の経済的評価
第4章 環境税制改革とポリシー・ミックスの経済評価―イギリスとドイツを事例として
第5章 欧州諸国のエネルギー関連税と環境税の比較制度分析
第6章 温暖化対策の国内制度設計―上流比例還元型排出権取引制度
第7章 温暖化ガスの排出権取引制度の政策効果―アメリカとEUの排出権取引制度の実績から
第8章 環境対策における差別的対応
著者等紹介
横山彰[ヨコヤマアキラ]
1949年、神奈川県に生まれる。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学、慶應義塾大学博士(経済学)。ヴァージニア州立ジョージ・メイソン大学公共選択研究センター客員研究員、城西大学経済学部助教授、などを経て、中央大学総合政策学部教授・学部長。専攻、財政および経済政策に関する公共選択研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。