- ホーム
- > 和書
- > 法律
- > 民法
- > 物権法・財産法・債権法
内容説明
軽妙な語り口で民法の奥行きを平明に説く。全面的に大幅加筆して共著とし、旧版から契約各論を独立。
目次
第1章 契約各論序論
第2章 贈与
第3章 売買
第4章 交換
第5章 消費貸借
第6章 使用貸借
著者等紹介
我妻榮[ワガツマサカエ]
明治30年米沢市に生まれる。大正9年東京帝国大学卒業。東京大学教授、東京大学名誉教授、法務省特別顧問。昭和48年10月逝去
川井健[カワイタケシ]
昭和2年広島市に生まれる。昭和28年東京大学卒業、北海道大学助教授・教授、一橋大学教授・学長を経て、一橋大学名誉教授
水本浩[ミズモトヒロシ]
大正9年熊本県に生まれる。昭和19年東京大学卒業。神奈川大学助教授、立教大学教授、獨協大学教授、立教大学名誉教授。平成11年12月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
80
少し契約関連のところを調べなければいけないので、総論よりも先に各論を読みました。ここでは贈与、売買、消費貸借などがわかりやすく説明されています。我妻先生亡き後そのお弟子さんたちが改訂をされていて今読んでも古臭くはありません。無味乾燥になりがちな法律の本を例示を多くして説明されています。いい本です。2019/04/07
えちぜんや よーた
22
金銭消費貸借の他、その他、贈与契約・売買契約などにも触れられています。「準消費貸借契約」(P136) すでに一方が何らかの債務を負っている時は、その債務に基づいて 消費貸借を成立させることができる。 つまり、貸し借りの事実があれば、「契約書」がなくても、 契約は成立している。典型例は、銀行預金。 ※ローマ法の時代には、厳格な証書の取り決めが、 契約の基準とされたそうですが、 時代が下るにつれて、形式的な要素が緩和され、 要物性(事実)が、重視されるようになったそうです 2012/10/25
-
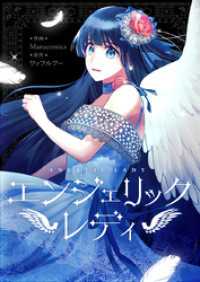
- 電子書籍
- エンジェリックレディ【タテヨミ】第15…
-

- 電子書籍
- この世は悪魔で沈んでる 31話 技術開…
-
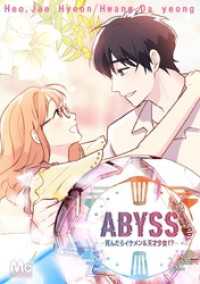
- 電子書籍
- ABYSS―死んだらイケメン&天才少女…
-

- 電子書籍
- 薬屋のひとりごと 3巻 ビッグガンガン…
-

- 電子書籍
- 規制の虜 グループシンクが日本を滅ぼす




