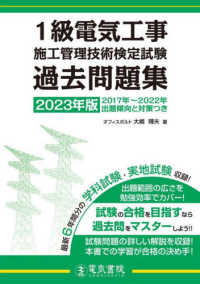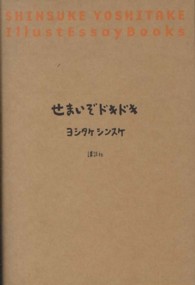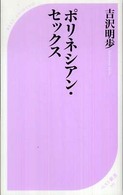内容説明
本書が扱うのは、「国家主権」をめぐる思想の歴史である。そこで描き出すのは、「立憲主義」の大きな流れが国際社会につくりだした変化の軌跡である。思想家たちは、われわれの生きる国際社会をどのように構想し、変えていったのだろうか。その起源と展開を追う。
目次
序章 国家主権が描き出す問題―前近代から近代へ
第1章 古典的立憲主義における主権概念―一七~一八世紀
第2章 国民国家確立と立憲主義的主権の変容―一九世紀
第3章 国際連盟と国際立憲主義の登場―二〇世紀の始まり
第4章 国際立憲主義の進展と挫折―二つの世界大戦のあいだ
第5章 国際立憲主義の停滞―冷戦・脱植民地化の時代
第6章 新しい国際立憲主義の萌芽―一九七〇年代~八〇年代
第7章 冷戦後世界における主権論―冷戦終結から二一世紀へ
終章 結論と展望
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
6
国民主権じゃないのかー。国家主権とは、国家だけに存する特別な属性(ⅰ頁)。ボダンの定義では、主権とは共和国の絶対的で永久的な権力(15頁)。ヘーゲルは国家を有機的組織とした(21頁)。ダイシーにとって憲法は、国家の主権権力の配分と行使に直接的・間接的に影響するすべての規則(95-96頁)。だから憲法は最高法規としての重要なのだ。ウールセイは、主権国家は権利について常に独立・平等(119頁)とした。ランシングは主権を卓越した物理的力の所有から生まれるとした(159頁)。主権が形式化され実質が問われる時代に。2013/04/23
とある本棚
4
難解。国際法や国際思想に関してかなりの前提知識が求められる。章を追うにつれて慣れ親しんだ国家主権概念に近づくことから理解しやすくなるが、前半の17世紀から20世紀の概念の変遷は理解できたとは言い難い。収穫はカールシュミットの主権概念の詳細を知れたことと、現代においてアメリカと欧州で主権に対する見方が「偽善(擬制)」と「制度」と異なっているという指摘。アメリカの「保護する責任」のスタンスの背後にある主権概念の理解が進んだ。昨今のウクライナ情勢は「国際立憲主義」に対する大きな脅威であることがよく分かった。2022/04/09
unpyou
1
「主権国家として…」という語りをときおり見かけるが、そもそも国家主権って何よ?と思い読んだ。絶対王政における国王が「神から与えられた」って説で主権独占してた時代から説き起こし「そもそも英国以外の国は半分しか主権持ってない」空気の帝国主義時代や、戦間期、国際連盟のため国家主権は制限される説の一方で「非常時の時に権力取れる奴が主権の所有者」と説いたナチ学者シュミットの説など、主権の定義がいかに転々と変遷してきたか分る。これ別に自明じゃねえなと理解できた。各々の思想は一読だけでは消化し難いのでもう一回拾い読もう2013/09/18