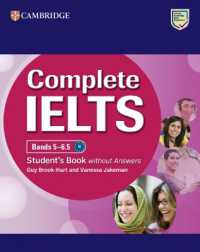内容説明
サンデルや現代コミュニタリアンは、なぜ今、古代からの西洋政治思想「共通善」を改めて説くのか。新たな実践哲学が、ここから始まる。
目次
第1章 共通善の政治学
第2章 共通善の政策学
第3章 コミュニティの思想史
第4章 コミュニタリアニズムと共和主義
第5章 ソーシャル・キャピタルとしての地域コミュニティ
第6章 コミュニタリアニズムの政策と共通善
著者等紹介
菊池理夫[キクチマサオ]
1948年青森県に生まれる。1976年慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程満期退学(法学博士)。現在、南山大学法学部教授。政治理論、ユートピア思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
4
「戦後の日本の社会科学では、村落共同体のような伝統的な「共同体」は、近代化のなかで解体されるのは当然である、むしろその方が進歩であり、望ましいという主張が強かったと思われる。政治学や行政学においても、伝統的な村落共同体は、閉鎖的で、権威主義なものであるとして批判され、特に第二のムラとして語られる町内会・自治会も…個人の権利や自由を束縛するものとして批判されることが多かった。…英米では一般的にコミュニティは、現代においても必要なものであり、それが消滅していくことは政治的・社会的にも損失であると思われている」2022/07/17
ひつまぶし
2
ようやく面白かった。コミュニタリアニズムの核心に共通善というキーワードを据えて、思想的な背景から現代的な意義まで広くまとめている。共通善とは、ほとんど認めるか認めないかの問題で、その上で「望ましい共通善とはどのようなものか」そして「どうすればそれを構築できるか」が常に課題としてつきまとう。ゆえにコミュニタリアンはプラグマティストでもあるのだろう。日本の地域主義に関する議論も興味深かったが、どこかで排除的な要素は引っかかる。もっともこれは、日本社会の特性はあっても、日本に固有の問題でないことも理解できる。2024/12/20
-

- 洋書
- RIEN DE RIEN