出版社内容情報
一つの脳の中でどのように二つの言語が共存できるのか。そして二言語の共存はどんな影響をもたらすのか。認知と言語を巡る探究の旅。
グローバル化と国際化が進む現代社会において、バイリンガリズムは重要性を増している。本書は二言語を使うことによって、注意や意思決定といった認知能力、あるいは脳構造・脳機能にどのような影響があるのかという興味深い疑問について、新生児の言語習得、脳機能イメージングなどの神経心理学的研究を通じ、多くの知見を紹介する。
【原著】Albert Costa, El cerebro bilingue: La neurociencia del lenguaje(Debate, 2017)
内容説明
一つの脳の中でどのように二つの言語が共存できるのか。二言語の共存はどんな影響をもたらすのか。認知と言語を巡る探究の旅。
目次
第1章 バイリンガルのゆりかご(ことばはどこにある?;どうしてこんなことされないといけないの?…二つの言語のつじつまがあわなかったらどうなる? ほか)
第2章 二つの言語、一つの脳(脳損傷とバイリンガリズム;二つの言語を画像化する ほか)
第3章 二つの言語を使うとどうなるか?(言語使用頻度と言語間の干渉;心的辞書 ほか)
第4章 バイリンガリズムは頭の体操(干渉を避ける;マルチタスキング、または、こちらからあちらへジャンプすると ほか)
第5章 意思決定(コミュニケーション上の文脈がすべてだ;言語と感情、あるいはことばで言い表したいことが表せないとき ほか)
著者等紹介
コスタ,アルバート[コスタ,アルバート] [Costa,Albert]
1970年生まれ。ポンペウ・ファブラ大学教授。Ph.D.(Psychology)専門はバイリンガリズムの認知プロセス、脳神経学的基盤の研究。2018年逝去
森島泰則[モリシマヤスノリ]
1958年、静岡県生まれ。1996年、コロラド大学大学院博士課程修了、Ph.D.(Psychology)。中学校教諭(英語)、日系企業研究員、スタンフォード大学客員研究員、国際基督教大学教養学部教授(心理学)を経て、現在は同大特任教授、および山梨英和中学校・高等学校長。専3門は認知心理学、とくに、第一、第二言語の文章理解(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三色かじ香
Go Extreme
-

- 電子書籍
- 不滅者の終活 第11話 - 第11話 …
-
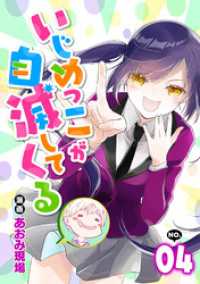
- 電子書籍
- いじめっこが自滅してくる4話 COMI…
-

- 電子書籍
- 0歳児スタートダッシュ物語 【フルカラ…
-
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2015年 8月号 - [ニッポン再発見の旅へ!]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0263815.jpg)
- 電子書籍
- Casa BRUTUS(カーサ ブルー…





