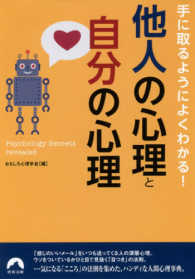出版社内容情報
知覚にまつわる言葉の相互関係を明確にし,哲学上の難問を解消する。知識論へと広がり,心の哲学に連なる問題の起点である。
【目次】
Ⅰ 信念の倫理学
第1章 認識的な用語
第2章 確からしさと明証
第3章 「基準」 の問題
Ⅱ 明 証
第4章 見え語の三つの用法
第5章 正当化と知覚
第6章 明証のいくつかの目印
第7章 明証について知ること
Ⅲ 知覚の対象
第8章 感覚すること
第9章 第二性質
第10章 物事の知覚
第11章 「志向的内存在」
付 論 現象論
内容説明
知覚にまつわる言葉の相互関係を明確にし、哲学上の難問を解消する。知識論へと広がり、心の哲学に連なる問題の起点。
目次
1 信念の倫理学(認識的な用語;確からしさと明証;「規準」の問題)
2 明証(見え語の三つの用法;正当化と知覚;明証のいくつかの目印;明証について知ること)
3 知覚の対象(感覚すること;第二性質;事物の知覚;「志向的内存在」;現象論)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ppp
0
所与性批判、オースティン、セラーズとの関連で。訳者の方が書いているように、議論の目的が明確ではないため、疑問文が出てくると、チザムがどちらを擁護しているのか理解しにくいことがある。訳者はチザムの立場を「内在主義的基礎づけ主義」としている。チザムがある意味で「内在主義」なのは概ね同意できるが、とりわけ「基礎づけ主義なのか」と自問すると、この本を読んだだけでは結構悩んでしまう。「何に対する基礎づけか」、「何のための基礎づけか」といった視点が限定的で、チザムの主張が知識、認識に容易に志向していないように見える。2014/04/06
-

- 洋書
- ROCK MACHINE