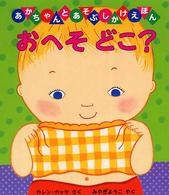出版社内容情報
名だたる学者たちが問い続けた「意識」という難問。神経生物学者と哲学者が手をとり、意識の進化研究を新たなステージへ押し上げる!
何があればその生物に「意識」があるといえるのか? 多くの研究者がこの「進化の目印」を求めている。神経機構か、感覚器官か。否。「学習」こそがカギだと喝破する著者二人は、脊椎動物、節足動物、頭足類をも射程に捉え、意識がカンブリア爆発と同時に進化したと推定する。動物意識の源流へと向かう緻密な探究をともに追随する体験!
内容説明
名だたる論者たちが問い続けた「意識」という難問。神経科学と哲学が共創する、新たな意識の進化論!
目次
1 理由づけと基礎づけ(目的指向システム―生命と意識に対する進化的アプローチ;心の組織化と進化―ラマルクから意識の神経科学まで;創発主義的合意―神経生物学からの視点;クオリアのギャップを生物学で橋渡し?;分布問題―意識はどの動物に備わっているのか?)
著者等紹介
ギンズバーグ,シモーナ[ギンズバーグ,シモーナ] [Ginsburg,Simona]
イスラエル・オープン大学元准教授。専門は神経科学
ヤブロンカ,エヴァ[ヤブロンカ,エヴァ] [Jablonka,Eva]
テルアビブ大学教授。専門は生物学の哲学
鈴木大地[スズキダイチ]
筑波大学生命環境系助教、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)客員研究員。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
プロムナード
yooou
mim42
gachin
Yoshi
-

- 電子書籍
- 私の青春シェアハウス~素直に生きてもい…