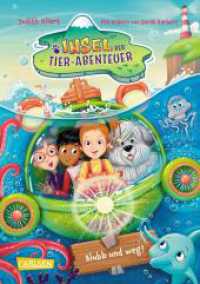出版社内容情報
アーレントは「政治とは何か」を生涯にわたって考え続けた。その答えの一つは他者と「行動をともにする」ことであると言えるだろう。しかしユダヤ人として故国を追われた彼女がポリスとナチスを同型としてしまうような両義的な政治を提示したのはなぜか。ハイデガーと祝祭概念を媒介してアーレントが論じた公共性の意義を考察する。
目次
まえがき
序 論――アーレントが語る「政治」とは何か
1 アーレントはどのように読まれてきたか
2 本書の目的
第1章 ワイマールにおけるハンナ・アーレント――戦間期ドイツの学知とアーレントの思想形成
1 序――ワイマール・ドイツ、あるいは破局の前の黄金時代
2 父親の喪失――「反抗」と「不安」
3 ハイデガーと「情熱的思考」
4 ヤスパースと「コミュニケーション」
5 「実存」と「愛の概念」
6 「政治」への覚醒――亡命、無国籍者、そしてアメリカへ
第2章 「全体主義」の誘惑に抗して
1 序――アーレント「全体主義」論の意義
2 「全体主義」における「全体」とは何か
3 世界の「全体」を再構築すること
4 結 び――「全体主義」という新たな「神話」
第3章 《祝祭》の政治学(1)――「公的領域」とは何か
1 序――アーレントの公共性をめぐる問題点
2 アーレントとファシズムとのあいだ
3 ハイデガーとアーレントの《ポリス-祝祭》
4 結 び――《祝祭》の政治学へ向けて
第4章 《祝祭》の政治学(2)――「敵/味方」の境界を越えて
1 序――政治空間における同一性/差異
2 アーレント「公的領域」の両義性
3 シュミットとアーレントにおける「再現前」と「公共性」
4 結 び――「再現前」と現代政治
第5章 「世界」の変革は可能か――「革命」論から見た「法」と「権力」
1 序――アーレントの「法」と「権力」
2 「創設」「始まり」としての「革命」と、そのアポリア
3 「法」「権力」の変動としての「革命」
4 結 び――《祝祭》としての「革命」
第6章 「物語」の可能性へ向けて――古代ギリシア〈ポリス〉の廃墟から
1 序――アーレントにとって古代ギリシアとは何か
2 「無支配」としての「ポリス=イソノミア」とその問題
3 アーレント/ハイデガー――「伝統」の破壊/再生
4 アーレント/ベンヤミン――「断片」と「配置」
5 ハイデガーとの断絶――「政治」と「哲学」との深淵
6 結 び――「物語」の多様性から可能性へ
第7章 「政治」と「哲学」とのあいだ――「全体性」としての政治、「世界性」としての政治
1 序――アーレントとシュトラウスにおける「政治」と「哲学」
2 ハイデガー以後の「政治」と「哲学」
3 「全体性」としての「政治」、「世界性」としての「政治」
4 新たな 「伝統」 の創出か、 あるいは 「伝統」 の破壊による再生か
5 結 び――「世界」と「全体」、二つの「公共性」
結 論
あとがき
参考文献
人名索引
事項索引
内容説明
公共性とは他者との間にその都度顕現する“祝祭”である。ハンナ・アーレントを通じて、リベラル・デモクラシー以前の「政治」の原初性を問い直し、ポストモダン以後に忘却された「公共性」の可能性を追う。
目次
序論―アーレントが語る「政治」とは何か
第1章 ワイマールにおけるハンナ・アーレント―戦間期ドイツの学知とアーレントの思想形成
第2章 「全体主義」の誘惑に抗して
第3章 “祝祭”の政治学(1)―「公的領域」とは何か
第4章 “祝祭”の政治学(2)―「敵/味方」の境界を越えて
第5章 「世界」の変革は可能か―「革命」論から見た「法」と「権力」
第6章 「物語」の可能性へ向けて―古代ギリシア“ポリス”の廃墟から
第7章 「政治」と「哲学」とのあいだ―「全体性」としての政治、「世界性」としての政治
結論
著者等紹介
石田雅樹[イシダマサキ]
1973年生まれ。2002年筑波大学社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。2005年学術博士(東京大学)。2004年4月~2007年3月独立行政法人日本学術振興会特別研究員(PD)。現在、明治大学法学部兼任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。