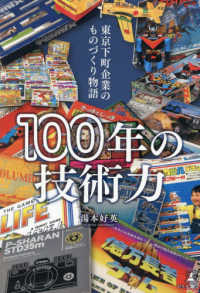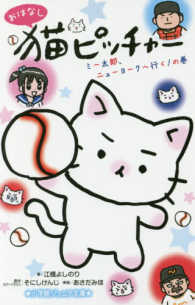出版社内容情報
言語および言語行為という場面に即して,現象学と分析哲学の間に見られる懸隔を架橋する。現象学には〈言語論的転回〉を,分析哲学には〈超越論的転回〉を要求して。
【目次】
Ⅰ 言語行為の現象学へ向けて
1 言語行為の現象学・序説
―現象学と分析哲学との対話を求めて―
2 「語る主体」と心身関係
―ストローソンの「人格」概念をめぐって―
3 言語・身体・意味
―ウィトゲンシュタインとメルロ=ポンティ―
Ⅱ 言語哲学から社会哲学へ
4 言語行為のの身体的次元
―「ホモ・シグニフィカンス」としての人間―
5 言語行為と対話的実践
―「言語ゲーム」から「終わりなき対話」へ―
6 言語行為の社会的次元
―ウィトゲンシュタインとハーバーマス―
Ⅲ 分析哲学と超越論哲学の狭間で
7 「言語ゲーム」の目指したもの
―ウィトゲンシュタインと超越論哲学―
8 超越論的語用論の射程
―英米哲学とアーベル、ハーバーマス―
9 「言語論的現象学」の可能性と限界
―オースティンとデリダ-サール論争―
10 現象学と分析哲学の交差と断絶
―ギルバート・ライルとフッサール、メルロ=ポンティ―
人名索引/事項索引
初出一覧
目次
1 言語行為の現象学へ向けて(言語行為の現象学・序説―現象学と分析哲学との対話を求めて;「語る主体」と心身関係―ストローソンの「人格」概念をめぐって;言語・身体・意味―ウィトゲンシュタインとメルロ=ポンティ)
2 言語哲学から社会哲学へ(言語行為の身体的次元―「ホモ・シグニフィカンス」としての人間;言語行為と対話的実践―「言語ゲーム」から「終わりなき対話」へ;言語行為の社会的次元―ウィトゲンシュタインとハーバーマス)
3 分析哲学と超越論哲学の狭間で(「言語ゲーム」の目指したもの―ウィトゲンシュタインと超越論哲学;超越論的語用論の射程―英米哲学とアーペル、ハーバーマス;「言語論的現象学」の可能性と限界―オースティンとデリダ‐サール論争;現象学と分析哲学の交差と断絶―ギルバート・ライルとフッサール、メルロ=ポンティ)
-

- 電子書籍
- 目が覚めたら30歳、新妻でした ~10…
-
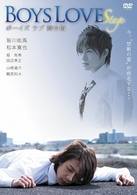
- DVD
- BOYS LOVE Stage