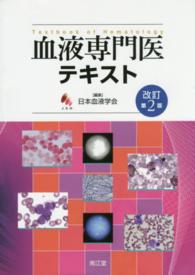出版社内容情報
構造主義からアクターネットワークセオリーまで、哲学と人類学という二つの知的実践は交錯してきた。その現代的な意義を考える。
ドゥルーズ=ガタリ、メルロ=ポンティ、サルトル、モース、デュルケム、ヴィヴェイロス・デ・カストロ、デスコラ、ストラザーン――いずれも「自然」をめぐり、レヴィ=ストロースの神話論理の再解釈や「構造」の捉えなおしとして進行してきた哲学と人類学について、思考様式の違いや歴史的な影響関係、主題の反復を浮き彫りにする。
内容説明
構造主義、存在論的転回、アクターネットワークセオリー、マルチスピーシーズ、パースペクティヴ主義、思弁的実在論etc―互いに利用し刺激を与えあう二つの研究分野。そのどちらもが「自然」へと向かい、「構造」を捉えなおす。本書は、レヴィ=ストロースの神話論理の再解釈を起点としながら、それぞれの思考様式の違いや対立だけでなく、歴史的な影響関係や主題の反復を浮き彫りにする。
目次
第1章 自分自身の哲学者になること―文化人類学と哲学が交錯する場所で
第2章 他者の認識と理解―「ネイティヴ」・文化・自然をめぐって
第3章 メラネシアからの思考
第4章 神話の精神分析/呪術のスキゾ分析
第5章 生成する構造主義―フィリップ・デスコラと野生の問題
第6章 構造とネットワーク―レヴィ=ストロース×ラトゥール
第7章 レヴィ=ストロースにおける階層と不均衡
第8章 レヴィ=ストロースの哲学的文脈―構造と時間/自然と歴史
第9章 デュルケムはパンドラの箱を開けたか―思考の非個人主義と非人間主義
著者等紹介
檜垣立哉[ヒガキタツヤ]
1964年生。大阪大学教授。博士(文学)。専門は大陸哲学やフランス現代哲学、日本哲学(主に京都学派)
山崎吾郎[ヤマザキゴロウ]
1978年生。大阪大学教授。博士(人間科学)。専門は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
PETE
文狸
-

- 電子書籍
- 魔王が田舎に嫁いだら【分冊版】 42 …