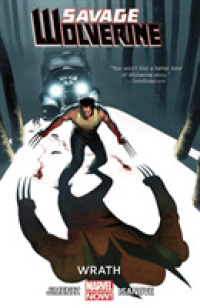出版社内容情報
ことばを交わす営みのなかで、私たちは実際には何を行っているのか。その構造を事象に即して記述する方法を模索する。新しい「コミュニケーションの哲学」の試み。
一九五○年代のオックスフォードで生まれた、オースティン-サール流の言語行為論と、意図やその認知にもとづくグライス流の「意味すること」の理論という二つの流れ。本書では両者を解釈しながら、個々の言語行為が生成・解釈されるプロセスを具体的に描写するための仮説的な理論を提示。コミュニケーションの実際のありように迫る。
[関連書] サール 『言語行為』、グライス 『論理と会話』 (勁草書房刊)
はじめに
序 章 「土曜日の朝」と一九五〇年代オックスフォード
1 「土曜日の朝の集い」とオースティン
2 「一九五〇年代オックスフォード」という場所
3 「言語コミュニケーションの哲学」へ
4 本書の目的
第Ⅰ部 言語行為論の三つのドグマ
第一章 一発話主義のドグマ――発語内の力はどこに宿るのか
1 三つのドグマとは
2 あらかじめ前提された一発話主義
3 一発話から会話シークエンスへ
4 「会話の格率」と会話シークエンス
5 一発話シークエンス
6 「言葉が意味すること」と「言葉をもちいて私たちが行うこと」
第二章 慣習主義のドグマ――オースティンの奇妙な論拠をめぐって
1 「規約」か「慣習」か
2 オースティンの奇妙な論拠(1)――行為遂行的発話と自己検証的言明
3 オースティンの奇妙な論拠(2)――あらかじめ前提された「中心からの道」
4 別様の道
第三章 「発語内の力」のドグマ――あらかじめ混同された二つの「力」
1 二つの「発語内の力」(1)――発話が発揮する力
2 二つの「発語内の力」(2)――発話を成り立たせる力
3 オースティンにおける「力」の両義性
4 両義性の要因と弊害――あるいは「分類表モデル」という描像
第Ⅱ部 話し手の意図について
第四章 グライスの重層的意図説
1 「意図」をめぐる二つの問い
2 なぜ重層的な意図なのか
3 グライス説は「強すぎる」のか
4 グライス説は「弱すぎる」のか――反例と意図の増殖
5 執行的意図とコミュニケーション的意図
6 重層的意図から相互顕在性へ――内的アプローチから離れて
第五章 意図主導型と慣習主導型
1 タイプ分けと話し手の意図
2 「意味すること」と「意味してしまうこと」
3 「内分け」構図と「外分け」構図
4 「外分け」構図の二つの問題点
5 「移行領域」そのものとしての慣習主導型言語行為
第六章 意図のミニマリズム
1 二種類の意図と構成的意図
2 執行的意図のミニマリズム
3 「世界との適合」論
4 構成的意図のミニマリズム
第Ⅲ部 発話解釈と行為生成
第七章 行為理解と発話解釈
1 ミニマリズムの限界と再構築の道
2 「意図の二つの顔」
3 行為戦略と行為理解
4 意図把握と解釈プロセス
第八章 発語内行為の生成
1 発話解釈のミニマリズム
2 発話解釈のプロセス(1)――行動タイプ~行為指示型
3 有標の発話と無標の発話
4 発話解釈のプロセス(2)――信念タイプ~主張型と心情表現型
5 発話解釈のプロセス(3)――信念タイプ~行為拘束型と宣言
終 章 言語とコミュニケーションの関係と無関係
1 発語内行為に結びつくもの
2 そもそもなぜ発語内行為なのか
注
あとがき
文献
索引
内容説明
ことばを交わす営みのなかで、私たちは実際には何を行っているのか?オースティン‐サールとグライスによる二つの理論を解釈しながら、言語コミュニケーションの構造を事象に即して記述する方法を探る。
目次
「土曜日の朝」と一九五〇年代オックスフォード
第1部 言語行為論の三つのドグマ(一発話主義のドグマ―発語内の力はどこに宿るのか;慣習主義のドグマ―オースティンの奇妙な論拠をめぐって;「発語内の力」のドグマ―あらかじめ混同された二つの「力」)
第2部 話し手の意図について(グライスの重層的意図説;意図主導型と慣習主導型;意図のミニマリズム)
第3部 発話解釈と行為生成(行為理解と発話解釈;発語内行為の生成)
言語とコミュニケーションの関係と無関係
著者等紹介
飯野勝己[イイノカツミ]
1963年埼玉県に生まれる。1989年東北大学大学院文学研究科博士課程前期修了。2006年東北大学大学院文学研究科博士課程後期修了。現在、平凡社勤務、埼玉県立大学・東洋大学非常勤講師。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buuupuuu
borisbear
-

- 電子書籍
- XAFSの基礎と応用 第2版 KS物理…