内容説明
予備知識ゼロからわかる、自治体AI活用入門書!
目次
序章 私たちの暮らしとAI(人工知能)
第1章 AI(人工知能)とは何か(「アルファ碁」の衝撃;AIの進化と第3次AIブーム ほか)
第2章 自治体におけるAI活用(情報提供型チャットボットAI;会議録作成、要約作業のAI ほか)
第3章 AI活用の可能性(野村総研報告書ショック;民間で起きている仕事のシフトと人材再配置 ほか)
第4章 AI新時代に自治体職員に求められるものとは(自治体職員数の推移;公務員に残る仕事―20年後の日本の自治体のイメージ ほか)
著者等紹介
稲継裕昭[イナツグヒロアキ]
早稲田大学政治経済学術院教授。大阪府生まれ。京都大学法学部卒。京都大学博士(法学)。大阪市職員、姫路獨協大学助教授、大阪市立大学教授、同法学部長などを経て、2007年より現職。政府委員・自治体審議会委員等多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バジンガ
4
現時点でのAIやRPAの実例が紹介されています。思ったよりも多くの自治体が取り組んでいることがわかります。ただ、自治体だけでは実現は無理で、大手ベンダーが絡んで進められています。オープンソースや職員で直営できるレベルまでできるといいですね。APIも公開されてますし。 #自治体 #AI2019/03/20
Micky
2
自治体の取り組んでいる業務の省力化。「AIで変わる‥」と銘打っているもののそれほどのものではない。RPAの例とチャットボット利用例が多く、問い合わせのシステム対応や住民票の出力自動化など現行のシステム利用の延長線上の技術で、まだまだAIというにはほど遠いレベルだ。画期的な事例はないものだろうか。確かに人は何人か人はきれそうだが自治体なんで派遣社員が割りを食う事になるんだろうと思う。こんなことでいいのかなあ。2019/07/26
ロク
1
あまりAIの導入事例を知らなかったので、「こんな事もできるんだ!」と新しい発見がありました。行政の事務は非効率だと言われてるし、実際そうだと思うし、任せるところはどんどんAIに任せられたらなぁと思いました。(突発的に発生した電話対応とかチャットボットでするとか)2020/05/12
ふーいえ
1
大手ベンダーがついているがどれだけの予算をつけてやっているのだろう?2019/07/23
Koji Suzuki
1
サービス業務において人工知能の果たす役割を「識別」「予測」「実行」の3要素で考える。既に「識別」においてはAIの方が早い。例えば住民票の発行。富士市役所二階の市民課窓口では大体15分程かかるけど、一階コンビニのマルチ機では5分以下。 今後ディープラーニングが進んで、「予測」機能が人間を上回る時代になれば、自治体業務の半分以上がAIに代替される。2019/05/08
-

- 電子書籍
- 傍観者、●●ちゃん【タテヨミ】第80話…
-
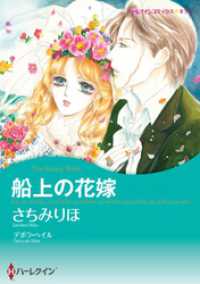
- 電子書籍
- 船上の花嫁【分冊】 2巻 ハーレクイン…
-
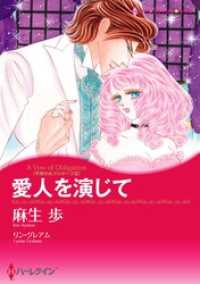
- 電子書籍
- 愛人を演じて〈予期せぬプロポーズIII…
-

- 電子書籍
- カバーいらないですよね 分冊版 19 …





