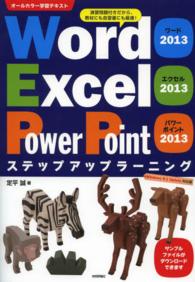内容説明
発達障害が原因でおこる失敗や挫折の繰り返しから、感情や行動にゆがみが生じ周囲を困らせる行動をとってしまう、それを二次障害と呼びます。その現れ方と非行化するプロセスとは驚くほど類似性があります。少年非行の現場で多くの発達障害児にも接してきた著者が、非行化のメカニズムの解説をもとに、二次障害の予防と対処を豊富な事例をあげて、わかりやすく紹介します。
目次
第1章 発達障害児の思春期
第2章 発達障害と二次障害
第3章 非行少年
第4章 二次障害としての非行化
第5章 二次障害の予防
第6章 実際場面での指導
著者等紹介
小栗正幸[オグリマサユキ]
岐阜県出身。法務省に所属する心理学の専門家(法務技官)として、犯罪者や非行少年の資質鑑別に従事し、福井、京都、大阪などの少年鑑別所や成人矯正施設に勤務した後、宮川医療少年院長を経て2009年3月退官。現在は特別支援教育ネット代表として、各地の教育委員会、学校、福祉関係機関、発達障害関連の「親の会」等への支援を行っている。特別支援教育士スーパーバイザー。専門領域は、思春期から青年期の逸脱行動への対応(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さなごん
20
耳の痛い話も多かった。生活支援、具体的にやり方を教える、なんでも「愛情不足」で片付けない、保護者との関係を改善するにはまず子どもとの関係づくり。2015/01/05
19May
7
タイトルは難解だが、内容は「非行少年が非行に走る理由と、それを防ぐ方法」であり、文体は親しみやすくわかりやすい。著者は心理学専攻の法務技官として各地の少年鑑別所で犯罪者や非行少年の資質鑑別に従事してきた。それだけに個々のエピソードや対応策がきわめて具体的なだけではなく、少年やその保護者への深い洞察と愛情が感じられる。著者は言う「(問題を起こした少年について)親の愛情が足りないという暗黙の酷評が日本中に蔓延し、多くの保護者が傷ついている」。示唆に富む良書。2012/06/29
ひろか
4
著者は、発達障害と非行の問題に取り組む中心人物である。 テキストはないか?との要望を受け、まとめられたもの。 基本的な考え方が整理できる。2010/06/02
KTakahashi
3
見立て(アセスメント)能力が試されます。盗癖も黙って借りたと考えてみる。いやいや,考えられません。アセスメントが見当違いでは,対応も的外れになってしまいます。2018/04/10
504
3
読みたかったのはまさにこんな本!2010/12/09