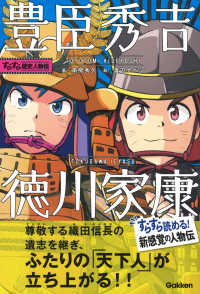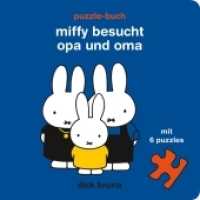内容説明
子供たちを豊かな感性と自主的で自発的なたくましい創造的知性をもつ、いきいきとした生活主体へと成長させていくことのできる“昭和60年代の新しい問題解決学習”を提唱。豊富な授業実践例を提示。「生活科」と「社会科」への新鮮な提言。
目次
第1章 急激な社会変化の中で子供像の変貌(子供らしさを失ってしまった子供たち;教育荒廃の社会的背景)
第2章 新しい社会科授業実践への展望(社会科実践に対する深い問いかけと豊かなイメージを;初期社会科における問題解決学習の意義と課題)
第3章 1980年代アメリカ社会科から学ぶもの(人間の普遍的本性についての学習としての低学年カリキュラムの再構成;文化と民族の多元主義に基づく国際的・地球的視野の形成;社会科学習の過程や方法の人間化;タバ社会科におけるグローバルな視野の育成と価値の分析・感情の探究・個人間の問題解決の具体的展開;バンクスの「知性的な社会的行為者」を育てる社会科授業構成論)
第4章 新しい問題解決学習による人間中心・人間本位の生活科と社会科の授業展開(人間理解・自己理解を培う低学年の新しい総合学習;生活科を楽しく新鮮で有意義な学習に;社会事象への興味・関心を高める観察と作業と体験的活動;人々の願い・価値の究明と人類的・地球的視野の形成;人間としての自立を促す中学校「高齢化社会がやってくる」の授業)
第5章 昭和60年代の新しい問題解決学習の確立を(人間中心・人間本位の新しい社会科学力像の確立;新しい問題解決学習による授業構成の視点)
-
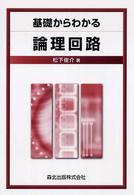
- 和書
- 基礎からわかる論理回路