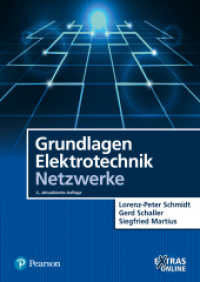- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
女というだけで学校で勉強する機会を奪われたくないとブログで訴え、タリバンに銃撃されたパキスタンの少女マララ・ユスフザイの児童向け伝記。回復した彼女は国連でスピーチし、ノーベル平和賞候補になった。
内容説明
2012年10月9日。15歳の少女が通学途中に銃撃にあった。少女の名は、マララ・ユスフザイ。ただただ、勉強がしたいと願う少女だった。奇跡的に生き抜くことができた一人の少女が、今、全世界に訴える。「すべての人に平和と教育を。教育こそただ一つの解決策」。
目次
序章
銃撃
ミンゴラ
ばく撃
目かくし鬼
お話
マウラナ・ラジオ
少女たち
市場
テレビカメラ
最後の日
退くつ
旅先にて
ホーム・スイート・ホーム
はかなき平和
学校にもどる
疎開
パキスタンへようこそ
トウモロコシの花
危機
目覚め
新しい人生
著者等紹介
マッツァ,ヴィヴィアナ[マッツァ,ヴィヴィアナ] [Mazza,Viviana]
1978年イタリア・カターニア生まれ。「コリエレ・デッラ・セーラ」紙のジャーナリスト。同紙のニュースデスクとして国際ニュースの社会系記事を担当
横山千里[ヨコヤマチサト]
文法指導に定評のあるイタリア語講師。テキストから作成に携わった通信講座を開講し、実務、文芸、映像字幕の翻訳も手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
179
マララはどこだ。神の兵士タリバンを侮辱した報復。座席は血で染まっていた。…女の子でも勇気があれば素晴らしいことができるという証明が名前にも刻まれている。…人を撃つことはできても、思い出や友情までを消し去ることはできない。学びを拒むこともできない。…自らの考えを言葉で伝えられる社会を求めている。本から学んだ思いやりの心、非暴力の哲学。父母から学んだ寛容の心。誰かが真実を語らなければならないという使命感。…暗闇に閉ざされたとき、光の大切さを知る。沈黙を強いられたとき、声の大切さを知る。教育には平和が必要です。2021/10/17
サク
77
『使命を自覚した人は強い』マララさんの見てきた環境は地獄そのもの。いじめを考える絵本『おおきなあな』の場面が浮かぶ。沢山の死の恐怖という『あな』に落ちないように歩く少年の姿が、パキスタンの人々に重ねることが出来る。『あな』を埋めようと思っても埋まらない。毎日死者がでる。恐怖で満たされる。死の恐怖という『あな』を埋めるのは、相手を憎むことでも銃で殺すことでもない。それはただ一つ教育の力である。本は永遠に残り、文字は銃で消えることはない。多くの人たちが勉強し賢くなると騙されない。強くなれる。平等に教育を。 2015/04/05
美紀ちゃん
77
人権の課題図書。最後の国連演説抄録に感動。そうだよね。戦争は本当に大変。 私たちは戦争を知らない。当たり前に学校に行って教育を受けたけど、それが叶わない子供たちが世界にはたくさんいる。アフガニスタン、パキスタンなどの紛争は、知っていなければいけない問題。マララ・ユスフザイさんはとても意志の強い勇気のある子。素晴らしい。お父さんもお母さんも良い人だった。世界でどのような問題が起こっているのか?知るために、必要な一冊。 2014/07/09
Miyoshi Hirotaka
73
過激な原理主義やテロリズムの勃興をイスラム社会固有の問題として理解するとその先に待ち構えるものは我々の社会との「文明の衝突」。ましてや、イデオロギー、民族、国家など分かりやすい一つの視点で説明できるものではない。相関性が高いのは教育。なかでも、識字率だ。どこの国でも男の識字率向上が先行し、それにより社会発展がもたらされるが、内乱や紛争という負の現象が同時に発生する。社会の安定は女の識字率向上と社会進出の度合いと相関する。この少女に起きたことは移行的危機。早く通過させるためには、教育支援が重要なのである。2014/11/01
ひらちゃん
62
ノーベル平和賞を受賞したマララ。銃撃を受けるまでの経過と、彼女の意思の礎がわかりやすく綴られた児童書。女子が教育を受けられない。強制的に婚姻されたり、戦争で子供たちの命を奪わない。終わりを始める為の運動を訴え続ける彼女の強さが伝わります。2016/11/09
-
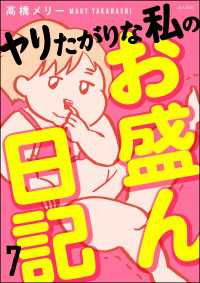
- 電子書籍
- ヤリたがりな私のお盛ん日記(分冊版) …