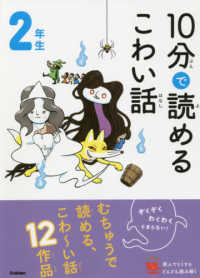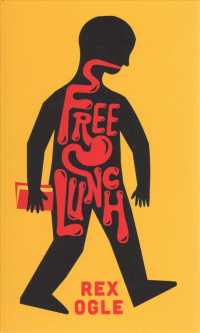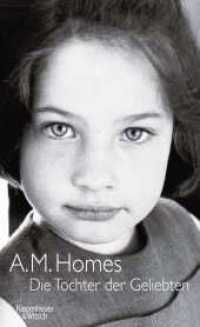出版社内容情報
目 次
第Ⅰ編 投資信託の基本概念
第1章 投資信託とは何か
1 投資信託の機能
(1) 投資信託の起源と特質
(2) 世界の投資信託商品
(3) 投資信託のメリット・デメリット
(4) わが国の投資信託の発展と機能の発揮
2 わが国の投資信託に関する法体系
(1) 金融ビッグバンと投資信託
(2) 1998年改正投信法
(3) 2000年改正投信法
3 投資信託の法的概念
(1) 証取法上の有価証券概念および投信法上の規定
(2) 投資信託の形態
(3) 契約型投資信託と会社型ファンド
(4) 証券投資信託、証券以外の投資信託
(5) 内国投信・投資法人、外国投信・投資法人
(6) 公募と私募
第2章 投資信託の機関
1 投資信託の機関に関する法務
(1) 投資信託の機関
(2) 投資法人の機関
2 投資信託委託会社の法務
(1) 投資信託委託会社の定義
(2) 投資信託委託業者の認可
(3) 投資信託委託業者の業務
(4) 投資信託委託業者の受託者責任
(5) 投資信託委託業者の行為準則
(6) 投資信託委託業者の兼業業務
3 投資信託の機関および投資信託委託会社の実務
(1) 投資信託産業の構造
(2) 投資信託委託会社の組織
第3章 投資信託のガバナンス
1 コーポレート・ガバナンス
(1) アメリカにおけるコーポレート・ガバナンス論議
(2) わが国におけるコーポレート・ガバナンス論議
2 投資信託におけるガバナンスの二つの視点
(1) 受益者、投資主によるファンドのガバナンス
(2) 運用に付随するコーポレート・ガバナンス
3 投資信託のガバナンスの法務
(1) 投資法人におけるガバナンス機構
(2) 投資信託におけるガバナンス機構
(3) 議決権行使
第Ⅱ編 投資信託の商品
第1章 ファンドの組成
1 ファンド組成の法務
(1) 委託者指図型投資信託
(2) 委託者非指図型投資信託
(3) 投資法人
(4) 私募ファンド
2 ファンド組成の実務
(1) 商品企画の実務
(2) 新設ファンドの状況(公募分)
(3) 私募ファンドの状況
3 ファンドのコスト
第2章 ファンドの形態分類
1 募集形態による分類
(1) 公募ファンド
(2) 私募ファンド
2 追加設定の可否による分類
(1) 単位型ファンド
(2) 追加型ファンド
3 途中解約の可否による分類
(1) オープンエンド型ファンド
(2) クローズドエンド型ファンド
4 投資対象による分類
(1) 証券投資信託
(2) 証券以外の投資信託
5 投資信託協会の商品分類
第3章 主要商品の概要
1 アクティブ運用ファンド
(1) グロースあるいはバリュー型ファンド
(2) バランスファンド
(3) TAAファンド
2 インデックス・ファンド
3 限定した投資範囲にのみ投資するファンド
4 MMF(マネー・マネジメント・ファンド)
5 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
6 中期国債ファンド
7 短期決算型公社債投信
8 長期公社債投信
9 ブル・ベアファンド
10 ファンド・オブ・ファンズ
11 ライフサイクル・ファンド
12 不動産ファンド
13 ETF(上場投資信託)
14 外国籍ファンド
第Ⅲ編 投資信託の販売
第1章 販売組織および販売員
1 証取法における規定
(1) 販売会社
(2) 外務員制度
(3) 内部管理責任者等
2 銀行法等における規定
3 投信法による規定
第2章 販売行為
1 販売の法務
(1) 行為規範原則・倫理綱領
(2) 適合性の原則、誠実公正義務
(3) 販売会社の禁止行為
(4) 目論見書制度
(5) 広告の法務
(6) 金融商品販売法
2 販売の実務
(1) 販売形態の変遷と販売業務
(2) 目論見書等販売に関連する資料
(3) 重要事項の説明
(4) 口座開設
(5) 約 定
(6) 報告書類
(7) 収益分配金の取扱い
(8) 解約・買取り・償還
(9) 証券事故の処理
第Ⅳ編 投資信託の運用
第1章 投資対象と投資制限
1 投資対象と投資制限に関する法務
(1) 投資対象
(2) 投資制限
2 投資対象に関する実務
(1) 投資対象のリスク・リターン
(2) 投資対象に関するその他のチェック・ポイント
第2章 運用の指図
1 運用の指図に関する法務
(1) 受託者責任
(2) 運用の指図にかかわる禁止行為
(3) 運用の外部委託
2 運用の実務
(1) 分散投資の意義とポートフォリオ理論
(2) 運用業務のフロー
(3) 株式投信の実際の運用
(4) 債券型投信の実際の運用
第3章 トレーディング
1 トレーディングに関する法務
(1) 受託者責任および禁止行為
(2) 禁止行為に関する施行規則の規定
2 トレーディングに関する実務
(1) トレーディングの位置づけ
(2) トレーディングの実務上のチェック・ポイント
第4章 リサーチ
1 リサーチの法務
(1) インサイダー取引の禁止
(2) 証券アナリスト職業行為基準
2 リサーチの実務
(1) バイサイド・リサーチとセルサイド・リサーチ
(2) マクロ調査とミクロ調査
(3) アナリストとファンド・マネジャーの関係
第Ⅴ編 投資信託のディスクロージャー
第1章 投資信託の発行開示
1 発行開示の法務
(1) 証取法における発行開示
(2) 目論見書の記載事項
(3) 有価証券届出書(目論見書)の効力発生期間と要約仮目論見書
(4) 投信法による発行開示
(5) 目論見書の電子開示
2 発行開示の実務
(1) 目論見書の作成と交付
(2) 洗練された発行開示資料への道
第2章 投資信託の継続開示
1 継続開示の法務
(1) 2法による継続開示規定
(2) 証取法による継続開示
(3) 投信法による継続開示
2 継続開示の実務
(1) 運用報告書の作成と交付・送付
(2) タイムリー・ディスクロージャー
第Ⅵ編 投資信託の管理
第1章 投資信託の計理
1 投資信託の計理業務の概要
2 投資信託計理の法務
(1) 投資信託法上の規定
(2) 投資信託協会の自主規制による信託財産の計理・組入資産の評価
3 投資信託計理の実務
(1) 投資信託計理業務のアウトライン
第2章 受益証券の発行管理
1 受益証券の発行管理の法務
(1) 投信法等による規程
(2) 印紙税法による課税
2 受益証券の発行管理の実務
(1) 受益証券の発行基準
(2) 受益証券の発行管理業務のアウトライン
(3) 主たる業務内容
(4) 効率的な受益証券管理のための留意・検討事項
第3章 ファンド監査
1 ファンド監査の法務
(1) 投資信託法等による規程
2 ファンド監査の実務
(1) 主たる業務内容
(2) 監査報告書の文例
第Ⅶ編 投資信託の外部評価
第1章 外部評価の意義と発展
1 ファンド評価の概要
(1) 外部評価(外部機関によるファンド評価)とは
(2) ファンド評価の必要性
2 監査法人によるファンド監査(外部監査)との違い
(1) ファンド監査のチェック項目
(2) ファンド監査とファンド評価の違い
3 ファンド評価機関の発展経緯
(1) アメリカでの評価機関の発展経緯
(2) わが国における評価機関
第2章 ファンド評価方法と利用の実務
1 定量評価の方法
(1) 5段階レーティングが一般的
(2) リターン(投資収益率)の計算方法
(3) 評価機関の定量評価方法例の一覧
(4) リスク指標の考え方と評価機関による方法の違い
2 定性評価の方法
(1) 定性評価の必要性
(2) 定性評価の方法例
(3) 定性評価の実際例
3 両評価法の有用性と限界
(1) 定量評価の有用性と問題点・限界
(2) 定性評価の有用性と問題点・限界
(3) ファンド評価の活用方法
4 運用会社の外部評価への対応
(1) 評価される側としての対応実務
(2) 評価結果活用の留意点
第Ⅷ編 投資信託の税制
第1章 ファンドに対する課税
第2章 公募証券投資信託の投資家に対する課税
1 個人投資家に対する課税
(1) 一律20%源泉分離課税を適用
(2) 追加型株式投資信託の個別元本方式
2 法人投資家に対する課税
(1) 収益分配金に対する源泉徴収
(2) 益金不算入
3 上場投資信託(ETF)の税制
第3章 公募証券投資法人の投資家に対する課税
1 個人投資家に対する課税
(1) オープンエンド型
(2) クローズドエンド型
2 法人投資家に対する課税
(1) オープンエンド型
(2) クローズドエンド型
第4章 私募証券ファンドの投資家に対する課税
1 個人投資家に対する課税
2 法人投資家に対する課税
第5章 不動産投信の税制
1 ファンド(公募クローズドエンド投資法人)に対する課税
2 投資家に対する課税
(1) 個人投資家
(2) 法人投資家の税務
第6章 そ の 他
1 優制度(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度)と投資信託
2 財形制度と投資信託
(1) 財形貯蓄制度
(2) 財形給付金および財形基金制度
3 投資信託と消費税
第7章 公募証券投資信託税制の推移
第Ⅸ編 投資信託と年金
第1章 欧米における確定拠出年金と投資信託
1 アメリカにおける確定拠出年金とミューチュアル・ファンド
(1) 確定拠出年金が投信成長の主要因
(2) 確定拠出年金と確定給付年金
(3) 401(k)とIRA
(4) 年金と投資信託
(5) 今後の展望
2 ヨーロッパの年金制度改革と投資信託
(1) イギリスの年金プランと投資信託
(2) ドイツの年金プランと投資信託
(3) スウェーデンの年金プランと投資信託
(4) 今後の展望
第2章 わが国における確定拠出年金の導入と投資信託
1 確定拠出年金の導入
2 確定拠出年金の商品と運用
第3章 個人金融資産における投資信託比率の上昇と年金、保険との関
係
1 先進諸国における投資信託比率の上昇
2 保険と投資信託
第Ⅹ編 投資信託50年発展史
第1章 戦後の投信復活までの前史
1 世界最初の投資信託
2 わが国の戦前の投資信託
3 戦後の投資信託再開
(1) 再開の背景
(2) 戦前の投資信託との違い
第2章 戦後の投資信託再開50年の概観
1 投信純資産の種類別推移
2 制度改革の推移
第3章 投資信託の勃興期から「40年証券不況」低迷期まで(1951~68
年)
1 好調なスタートから償還延長の試練へ(1951~55年)
(1) スタート時の投資信託;単位型株式投資信託
(2) 好調なスタート
(3) 1954年の償還延長
2 投資信託ブーム(1955~62年)
(1) 株式投信の急成長
(2) 投資信託委託会社の独立
(3) 公社債投信の開始と低迷
3「(昭和)40年証券不況」下の深刻な低迷(1963~68年)
(1) 不振続く株式投信
(2) 「日本共同証券」、「日本証券保有組合」の発足
(3) (昭和)40年証券不況
(4) 安定運用指向となる単位型投資信託
(5) 1967年の投信法の一部改定
第4章 投資信託の躍進期(1968~89年);商品の多様化と株式投信の
急増
1 商品多様化の進展
(1) 運用対象面での多様化
(2) 投資信託スキーム面の多様化
2 海外証券投資の開放
3 スポット型投信の登場
4 ファミリー・ファンドの新設
5 「列島改造」ブーム
6 石油ショックの影響と意味
(1) 第1次石油ショック
(2) 第2次石油ショック
7 公社債投資信託の拡大と多様化
(1) 多様化の背景
(2) 中期国債ファンドの誕生
(3) 高金利時の公社債投信の発展
(4) 好調な長期公社債投信、中期国債ファンド
(5) FFF(フリー・ファイナンシャル・ファンド)の登場
8 飛躍期に入る株式投信と多様化の進展
(1) その背景
(2) 法人向け大口投信の設定
(3) 1986年の規制緩和
(4) アメリカのブラック・マンデー
(5) クオンツ型運用の登場
(6) スポット型投信の拡大
(7) 投資信託研究会の指針
第5章 投信ビッグバン期(1990年以降)
1 バブル崩壊で激減する株式投信
(1) 株式投信純資産残高は7年連続減少、ピークの約5分の1へ
(2) 償還延長と乗換手数料割引
(3) オープン型にシフトする株式投信
2 MMFの誕生と公社債投信の多様化
(1) 1992年にMMF誕生、コア商品に
(2) 好調な公社債投信
(3) 証券総合口座向けMRFの誕生
(4) 非上場債券の時価評価へ
3 投信ビッグバン――進む制度改革
(1) 1992年:投信委託業務への参入促進
(2) 1994年の投信改革
(3) 1996年以降の金融ビッグバン
4 投信委託会社と販売チャネルの拡大
(1) 投信委託会社の拡大
(2) 銀行窓販など販売チャネルの多様化
5 拡大する金融ビークルとしての投資信託の役割
内容説明
商品設計、販売、運用、管理、評価、税務等、投資信託の実務を法務の視点で体系的にまとめた待望の実務書。金融機関、一般事業会社、運用機関、大学生必携の諸。
目次
第1編 投資信託の基本概念
第2編 投資信託の商品
第3編 投資信託の販売
第4編 投資信託の運用
第5編 投資信託のディスクロージャー
第6編 投資信託の管理
第7編 投資信託の外部評価
第8編 投資信託の税制
第9編 投資信託と年金
第10編 投資信託50年発展史