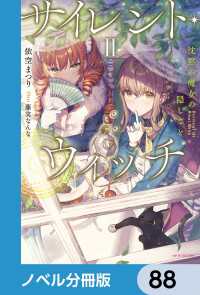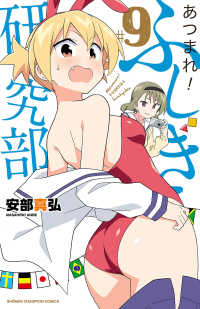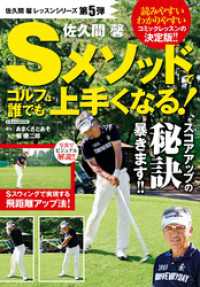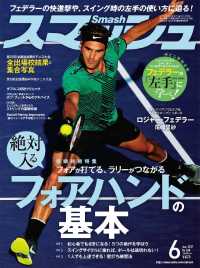出版社内容情報
好評の『SPC法 新法解説と活用法』(1999年刊行)を平成12年5月23日の法律改正を受けて全面改訂。
資産流動化法(改正SPC法)、改正投信法など法律の最新情報(中央省庁再編をはじめ平成13年4月1日施行まで)を網羅! さらに、関連する経済指標等のデータも最新の情報を掲載し、活用枠を大幅に拡大!
SPC(特定目的会社)、SPT(特定目的信託)、投信(資産運用)の実務活用に必要な知識を完全収録! 最新のビジネス情報・将来展望に至るまで資産流動化・不動産証券化のプロセスをわかりやすく解説!
金融機関職員をはじめ、不動産・地方公共団体関係者必読の書!
第1部 解説編
第1章 資産流動化法の予備知識
Q1SPC法改正のポイントは何か、また改正法はどのような法律か/Q2 特定目的会社(SPC)は一般の株式会社と何が違うのか/Q3 資産対応証券にはどのようなものがあるか/Q4 資産対応証券を取り扱うことの出来る者はだれか/Q5 投資家はどのように保護されるのか
第2章 資産流動化の予備知識
Q6 なせ、SPC法は改正されたのか/Q7 資産流動化のスキームはどうなっているのか/Q8 資産流動化のメリットは何か/Q9 資産流動化スキームが有効に機能するためのポイントは何か/Q10 米国における資産流動化の歩みはどうなっているのか/Qll わが国における資産流動化の歩みはどのようなものか
第3章 特定目的会社活用のための実務
Q12 特定目的会社(SPC)を設立・届出するための要件はどのようなものか/Q13 資産流動化計画とは、その記載事項や変更・終了の手続はどうなっているのか/Q14 特定目的会社(SPC)の社員の権利義務はどうなっているのか/Q15 特定目的会社(SPC)における社員総会、取締役、監査役、会計監査人の役割はどのようなものか/Q16 特定目的会社(SPC)の解教・清算に必要な手続はどうなっているのか
第4章 特定自的信託活用のための実務
Q17 特定目的信託とはどのような制度か/Q18 資産信託流動化計画とは、その記載事項や変更・特定目的信託終了の手続はどうなっているのか/Q19 受益権の譲渡や受益証券の権利者はどうなっているのか、権利者集会の役割は/Q20受託信託会社等の権利義務はどのようになっているのか/Q21 特定目的信託契約の変要・解除・終了に必要な手続はどうなっているのか
第5章 改正投信法の解説と活用のための実務
Q22 わが国における投資信託制度の歩みはどのようなものか/Q23 投信法改正のポイントは何か/Q24 新投信法における資産運用スキームはどのようなものか/Q25 投信スキームヘの参加者とその役割とは:その1-投資信託委託業者/Q26 投信スキームヘの参加者とその役割とは:その2-投資法人/Q27 投信スキームヘの参加者とその役割とは:その3-その他/Q28 投資家はどのように保護されるのか
第2部 将来展望
第6章 資産流動化市場の現状と展望
Q29 中小企業向け貸付債権流動化は実現するのか/Q30 売掛債権を活用した資産流動化は軌道に乗るのか/Q31 ノンバンクの資金調達構造はどうなるのか/Q32 住宅ローン債権の流動化は軌道に乗るのか
第7章 不動産証券化の展望(動きだした日本版リート)
Q33 不動産証券化の発展の経緯はどのようなものか/Q34 不動産証券化の経済的意義はどのようなものか/Q35 不動産証券化商品の供給実績とその商品特性とは/Q36 米国のREITと日本版リートの相違点は何か/Q37 日本版リート(不動産証券化)を取り巻く課題/Q38 不動産証券化を取り巻く新たなビジネス
内容説明
不動産証券化・不動産投資信託(日本版REIT)を詳細に解説!改正SPC法(資産流動化法)、改正投信法など法律の最新情報(中央省庁再編をはじめ平成13年4月1日施行まで)を網羅。新しい不動産ビジネススキームをわかりやすく解説。金融機関職員をはじめ、関係者必携の書。
目次
第1部 解説編(資産流動化法の予備知識;資産流動化の予備知識;特定目的会社活用のための実務;特定目的信託活用のための実務;改正投信法の解説と活用のための実務)
第2部 将来展望編(資産流動化市場の現状と展望;不動産証券化の展望(動きだした日本版リート))
著者等紹介
山崎和哉[ヤマザキカズヤ]
1969年生まれ。92年東洋信託銀行入社。99年三和総合研究所へ出向。現在金融ソリューション部研究員。主要研究テーマは、中小企業金融、不動産証券化、BtoBEコマース決済戦略など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。