出版社内容情報
放射線計測はその初期から放射線や放射能の利用に道を拓いてきた。現代では、エネルギー技術としての原子力発電、核医学や放射性医薬品学などの医学利用、製造業での品質管理や工程管理での利用、食品の放射線照射による保存性の確保など、社会に直結した様々な技術を支える存在となっている。
こうした実務領域での多様性を考慮し、まず共通の基礎となる事項を前半で解説する。Chapter 1~3 では、放射線と放射能の性質、放射線計測についての基礎的な概念を中心に解説する。Chapter 4~6 では、γ 線スペクトロメトリーや液体シンチレーション検出装置などの現代の分析実務の場で中核的な役割を演じている計測技術を中心に解説、Chapter 7 では放射線計測の感度が低下する長半減期核種の分析に向いた質量分析(粒子計測)を取り上げる。後半では、より具体的な計測技術や分析手法の応用について、対象試料や分析ニーズを意識しながら解説する。Chapter 8、9 では環境放射能分析を扱う。この分野での放射線計測のニーズは福島第一原子力発電所事故を契機に急激に増加した。また、今後も環境回復プロセスの進行を支える基盤技術の一つとして重要な役割を担うこととなる。Chapter 10~12 では放射線や放射性核種を利用した分析法に焦点を当てる。Chapter 10 では非放射性の微量元素分析の代表的手法の一つである放射化分析、Chapter 11 は放射性トレーサーを利用する分析手法であるラジオイムノアッセイなど、Chapter 12 は状態分析あるいはキャラクタリゼーションの手法としても発展してきたメスバウアー分光法、陽電子消滅、中間子利用分析、ラザフォード散乱などに焦点を当てる。
本書が日頃から分析技術を担う方々の手の届く所に置かれ、より高度な知識を扱う専門書や文献などを扱う際の一助となればと思う。また、新たな分析ニーズに対処する際に、放射線計測技術の利用についてのヒントを与えるものとなればとも思う。
目次
1 放射線と放射能
2 放射線の発生と検出
3 分析実技としての放射線計測
4 放射線計測データの取り扱い
5 標準物質
6 放射性核種の化学分離
7 質量分析法による放射性核種分析
8 環境放射能:方法論
9 環境放射能:分析例
10 中性子放射化分析
11 放射性同位体の化学反応を利用する分析法
12 放射線計測に基づくキャラクタリゼーションの手法
付録 放射線関連データ
著者等紹介
藥袋佳孝[ミナイヨシタカ]
1982年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。現在、武蔵大学リベラルアーツアンドサイエンス教育センター教授、理学博士。専門:放射化学、核分析化学、ランタノイド化学・アクチノイド化学
久保謙哉[クボケンヤ]
1989年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。現在、国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科教授、理学博士。専門:放射化学、分析化学、量子ビーム科学
桝本和義[マスモトカズヨシ]
1978年東北大学大学院理学研究科博士後期課程中退。現在、高エネルギー加速器研究機構・総合研究大学院大学名誉教授、理学博士。専門:核化学、放射分析化学、放射線安全管理学
三浦勉[ミウラツトム]
1989年群馬大学大学院工学研究科修士課程修了。現在、産業技術総合研究所計量標準総合センター、博士(理学)。専門:分析化学、放射化学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
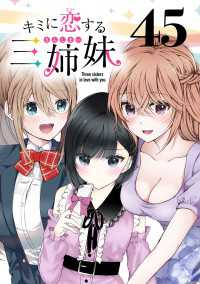
- 電子書籍
- キミに恋する三姉妹(話売り) #45 …



