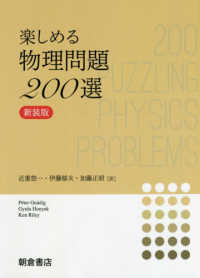出版社内容情報
マイクロエレクトロニクスの発展によって,コンピュータがますます高性能,低価格,小型化し,世の中至る所にコンピュータが存在する「ユビキタスコンピューティング」,また,地球上どこにでも浸透して存在を気にする必要がない「パベイシブコンピューティング」の時代が到来した。現在のコンピュータの代表であるパソコン,タブレットコンピュータ,そして,ほとんどの人が利用しているスマホ,それらが,ネットワークを介して,Webサーバなどと,それぞれが有機的に関係しつつ,統合的にシステムを形作っており,これらの基本となる技術が,本書で述べる分散システムである。
分散システムは,コンピュータとネットワークの両者を統合化するための技術であり,本来1台単独で動いていたコンピュータをネットワークで結び付けようとするものである。それも単に回線で結び付けるものでなく,複数のコンピュータを相互に有機的に結び付け,全体が巨大な情報システムとして動作させるものである。このような分散システムを実現するためには,分散システムアーキテクチャ,プロセス,クライアントサーバ,通信,名前付け,同期,一貫性と複製,フォールトトレラント性,セキュリティ,分散ファイル,オブジェクト,分散Webシステム,パーベイシブシステム,分散組み込みシステム,密結合型分散システムなど各種の新しい技術が必要となってくる。これら技術を本書ではわかりやすく,かつ親切に説明している。
第1章 分散システムの概要
1.1 分散システムの定義
1.2 目的
1.3 分散透過性
1.4 開放性
1.5 分散システムの制約
第2章 分散システムの種類
2.1 分散コンピューティングシステム
2.2 分散情報システム
2.3 パーベイシブシステム
第3章 アーキテクチャ
3.1 アーキテクチャ型
3.2 システムアーキテクチャ
第4章 プロセス
4.1 プロセスとスレッド
4.2 仮想化
4.3 コードマイグレーション
第5章 クライアントサーバ
5.1 クライアント
5.2 サーバ
5.3 ソケット通信
第6章 通信
6.1 ネットワークアーキテクチャ基本技術
6.2 OSI参照モデルと基本機能
6.3 TCP/IP参照モデルと基本機能
6.4 遠隔手続き呼び出し
第7章 名前付け
7.1 名前・アドレス・識別子
7.2 フラットな名前付け
7.3 構造化された名前付け
7.4 属性ベース名前付け
7.5 名前付けに関する最近の事例
第8章 同期
8.1 クロック同期
8.2 論理クロック
8.3 排他制御
8.4 選任アルゴリズム
第9章 複製と一貫性
9.1 複製とスケーラビリティ
9.2 データ中心一貫性モデル
9.3 複製管理
9.4 一貫性プロトコル
第10章 フォールトトレラント性
10.1 フォールトトレラント性の導入
10.2 プロセスの回復力
10.3 高信頼クライアントサーバ間通信
10.4 高信頼グループ間通信
10.5 分散コミット
10.6 回復
第11章 セキュリティ
11.1 情報セキュリティの特性
11.2 暗号
11.3 セキュアな通信路
11.4 アクセス制御
11.5 セキュリティ管理
第12章 分散ファイルとオブジェクト
12.1 分散ファイルシステムアーキテクチャ
12.2 分散ファイルシステム
12.3 分散オブジェクト技術
第13章 分散Web システム
13.1 歴史
13.2 システム形態
13.3 動作の仕組み
13.4 HTTP
13.5 実用化のための工夫
13.6 コラボレーションへの発展
第14章 パーベイシブシステムと分散組み込みシステム
14.1 組み込みシステム(パーベイシブシステム)とは
14.2 組み込みシステムにおける分散処理
14.3 OSと割り込みの関係
14.4 ASMP型の組み込みシステム
14.5 密結合組み込みシステムにおける細粒度排他制御
14.6 ASMP型分散組み込みシステムにおける排他制御の課題
第15章 密結合型分散システムにおける排他制御
15.1 ソフトウェアによる排他制御
15.2 ソフトウェアによる不正な排他制御
15.3 ソフトウェアによる正しい排他制御
15.4 マルチCPU対応命令を利用した排他制御
15.5 RMWサイクル命令の利用
15.6 LL,SC系の命令の利用
目次
分散システムの概要
分散システムの種類
アーキテクチャ
プロセス
クライアントサーバ
通信
名前付け
同期
複製と一貫性
フォールトトレラント性
セキュリティ
分散ファイルとオブジェクト
分散Webシステム
パーベイシブシステムと分散組み込みシステム
密結合型分散システムにおける排他制御
著者等紹介
水野忠則[ミズノタダノリ]
1969年3月名古屋工業大学経営工学科卒業。1969年4月三菱電機株式会社入社。1987年2月九州大学(工学博士)。1993年4月静岡大学教授。2011年4月‐現在、愛知工業大学教授、静岡大学名誉教授。受賞歴:情報処理学会功績賞(2009)ほか。学会等:情報処理学会員、電子情報通信学会員、IEEE会員、Informatics Society会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。