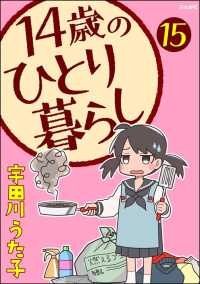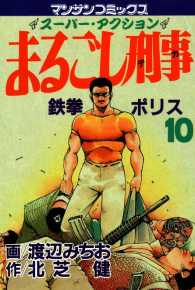出版社内容情報
本書『微積のあたま』は微分積分学の入門的な教科書である。内容は集中形式、学び方はゆったりとした参考書である。それと同時に微分積分学がいかにすばらしいものであるかを示す、いわば微積礼賛の書である。
微分積分の最初に(あたまに)学ぶべきスタンダードな項目をしっかり押さえた中で、とくに最初に理解すべき項目、とくに重要な項目、間違えやすい項目に的を絞って、ていねいに解説している。何事も最初が肝心なので、頭ごなし、理不尽、問答無用、というものではなく、ていねいでリーズナブルな説明を心がけた。高校の教科書では触れられない視点、大学の教科書では省略される背景も述べるようにした。読み進めていくうちに、「微積のあたま」が自然に鍛えられるような本を目指した。
本書は自習書や学び直しのテキストとしても使うことができる。演習問題によって自身の理解度を確認し、余談やコラムを通して関連する話題や背景を知ることができる。イラストもあって息抜きできる。この本を読むことで、高校数学で微分積分を学んだ気になっている人よりむしろアドバンテージをもつことができる。
あらゆる自然科学の基礎となる微分や積分の意味合いや考え方を楽しく学び、さらに高度な数学や応用をよりよく理解することに役立つ。
あまた微積の本あれど
微積のあたまはこれひとつ
目次
第1章 関数(多項式関数、有理関数、代数関数;指数関数と対数関数;三角関数、逆三角関数;関数の極限値;連続関数)
第2章 微分(微分係数;導関数;平均値の定理;不定形極限;関数の増域、臨界点、極大・極小)
第3章 積分(不定積分;定積分;定積分の応用;曲線の長さ;広義積分)
第4章 偏微分(多変数連続関数;偏微分と偏導関数;高階の偏導関数;極値問題)
第5章 重積分(2重積分;累次積分;重積分の変数変換;3重積分;広義重積分)
付録A 実数と数列
付録B 関数、微分、積分の補足
著者等紹介
石川剛郎[イシカワゴウオ]
1985年京都大学大学院理学研究科博士課程数学専攻修了。現在、北海道大学大学院理学研究院数学部門教授。北海道大学電子科学研究所附属社会創造数学研究センター教授(兼任)。理学博士。専門は幾何学(特異点論、トポロジー、実代数幾何、サブリーマン幾何)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。