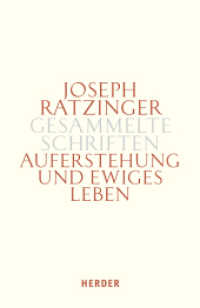出版社内容情報
円周率πはどのようにして導き出されるのか。
小学校の算数の教科書には,円周率πの値は3.14として出てくる。しかし,このπの値をどのようにして導出してきたかは,大学を卒業してもよくわからない。そこで,大学初級程度の能力で理解できる書物が必要と考え,本書をまとめた。高校生,大学生,さらには興味ある社会人に役立つことを願っている。
1.円周率πを求めよう
2.πを導出するために必要な微分
3.πを導出するために必要な積分
4.近似式と近似値
目次
1 円周率πを求めよう(円周率π=3.14159…を求めよう;図形から円周率πを求めよう)
2 πを導出するために必要な微分(数列と級数;導関係;マクローリン展開)
3 πを導出するために必要な積分(積分の基本公式;三角関数や指数関数の不定積分;逆関数の不定積分;逆関数とべき級数の積分)
4 近次式と近似値(関数f(x)=√1+x
関数f(x)=ex
関数f(x)=sin x
関数f(x)=cos x
平方根の求め方)
著者等紹介
木田外明[キダソトアキ]
1949年石川県生まれ。1975年金沢大学大学院工学研究科修士課程修了。1983年東京工業大学より工学博士授与。現在、金沢工業大学数理工教育研究センター教授。専門分野、計算数学、材料力学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。