出版社内容情報
●内容
1998年、治験への取り扱いに関する取り決めがICHにおいて世界的レベルで行われ、国際的に認められる倫理的、科学的かつ信頼性のある臨床試験を行う環境整備が求められるようになった。我が国ではこれを受けて、薬事法を改正し、新GCP省令に基づく治験が開始された。これらの社会環境の変化の中で、治験業務における医師以外の職種の役割も拡大し、新しく治験の管理的業務を担うCRCやCROの役割も注目されるようになった。 一方、日本薬学会薬学協議会モデルカリキュラム案には「医薬品を創る」、「医薬品開発と生産のプロセス」が大項目としてあげられ、その中には「治験における薬剤師の役割」も含まれている。ここでは薬学生が将来、医薬品開発に参画できるようになるためには、医薬品を支えるサイエンスや医薬品開発の各プロセスについて学ぶ必要があるとし、それらに関する基本的知識と技能の修得を一般目標としている。
これらの社会的背景を踏まえ、医薬品開発から市販後臨床試験に到る過程の中で、医薬品の有効性と安全性の確保にかかわる基本的知識の習得を目的に本書を編集した。構成は11章からなり、その内容は医療と倫理、日本の医療、医薬品産業、日本の薬事行政、特許制度、医薬品を支えるサイエンス、非臨床試験、臨床試験(治験)、医薬品の承認、市販後の有効性・安全性確保、医薬品の評価法である。とくに、医薬品開発に関わる業務を担う人々がその役割と責任について考える態度を身に付けることの重要性を鑑み、医療倫理、企業倫理も含め、幅広い内容とした。
●目次
1章 医療と倫理
1.1 ヒトを対象とする試験に関する倫理
1.2 薬害からの教訓
1.3 医薬品の倫理性
1.4 新薬開発のプロセスにおける倫理
1.5 薬を使う立場における倫理
1.6 医療倫理
1.7 臨床試験依頼に対する薬剤師の対応(ワークショップ事例)
2章 日本の医療
2.1 医療制度
2.2 医療制度改革
3章 医薬品産業
3.1 日本の医薬品産業
3.2 日本と世界の医薬品産業の比較
4章 日本の薬事行政
4.1 厚生労働省の主な組織と役割
4.2 薬事法改正の経緯
4.3 薬事関連の法規制
4.4 研究開発促進のための施策
4.5 創薬における特許権
5章 特許
5.1 医薬品開発における知的財産権
5.2 日本の特許制度
6章 医薬品を支えるサイエンス
6.1 患者を中心に考えた医療
6.2 医薬品創製の歴史
6.3 先端技術を用いた医薬品開発
6.4 医薬品開発に関する環境の変化
7章 非臨床試験
7.1 非臨床試験の目的
7.2 非臨床試験の概要
7.3 毒性試験に関する省令およびガイドライン
8章 臨床試験(治験)
8.1 臨床試験の一般指針
8.2 臨床試験の概要
8.3 目的別試験
8.4 ブリッジング試験
8.5 医療用具の臨床試験
8.6 医師主導型治験
8.7 医薬品の臨床試験の実施に関する基準
8.8 医療機関における治験業務
9章 医薬品の承認
9.1 医薬品の製造承認・許可制度
9.2 医療用医薬品の製造承認
9.3 一般用医薬品の製造承認
9.4 薬価基準収載のプロセス
10章 市販後の有効性・安全性確保
10.1 GPMSPの概要
10.2 市販後調査
10.3 医療用医薬品添付文書情報
11章 医薬品の評価法
11.1 生物統計の基礎
11.2 臨床への応用
付録1:医薬品開発関連薬剤師国家試験問題と解説
付録2:略語集
目次
1章 医療と倫理
2章 日本の医療
3章 医薬品産業
4章 日本の薬事行政
5章 特許制度
6章 医薬品を支えるサイエンス
7章 非臨床試験
8章 臨床試験(治験)
9章 医薬品の承認
10章 市販後の有効性・安全性確保
11章 医薬品の評価法
著者等紹介
安生紗枝子[アンジョウサエコ]
1961年明治薬科大学卒業。1992年東邦大学医学部付属大森病院薬剤部長を経て、現在、東邦大学薬学部教授・薬学博士
佐藤光利[サトウミツトシ]
1990年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了。現在、東邦大学薬学部助教授・薬学博士
渡辺宰男[ワタナベスズオ]
1959年東京工業大学理工学部化学課程卒業。1959年~1961年東京大学農学部有機化学教室研究生。1992年明治製菓(株)薬品総合研究所長、1995年常務取締役薬品開発本部長を経て、現在、明治製菓(株)顧問(薬品研開本部)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
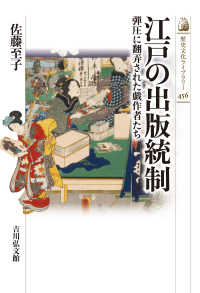
- 電子書籍
- 江戸の出版統制 - 弾圧に翻弄された戯…
-

- 電子書籍
- パチスロ115番街 4
-
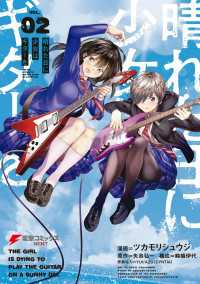
- 電子書籍
- 晴れた日に少女はギターを 2 電撃コミ…
-
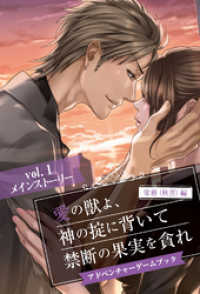
- 電子書籍
- 愛の獣よ、神の掟に背いて禁断の果実を貪…
-
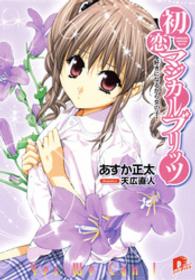
- 電子書籍
- 初恋マジカルブリッツ13 好きになるか…




