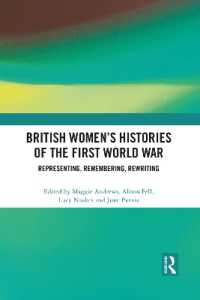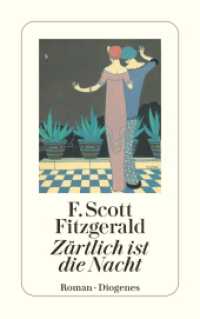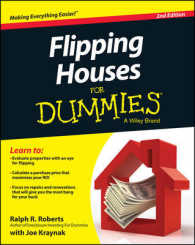出版社内容情報
森の中で普段目に見えない地下部の世界では,樹木が「根」を土壌に張り巡らすことで,生態系を作りだし,森を支えている。樹木の根は,太い根で体を支え,隣り合う樹木の根でネットワークを作ることにより,表層崩壊や土砂流出を防ぐなど,様々な災害から国土を保全するという減災の役割を果たす。樹木の細い根は,生存に不可欠な養水分を吸収し,森林における物質・水循環を駆動する。自ら動くことのできない樹木は,変動する環境下で根を変化させながら適応し,土壌中の生物と共生することで生育する。すなわち樹木の根が,様々な生態系サービスを発揮する森林を,見えない土壌の中で支えているといえる。
森の根に関する知見は,林業で対象とされてきた幹や葉に比べ著しく少なく,研究も立ち遅れており,樹木の根に関する教科書は,これまでほとんど例を見ない。本書は,「樹木の根を対象とする唯一の教科書」として,第一線の研究者が,樹木の根に関する基礎的知見について網羅的に,その手法や最新動向とともに紹介することで,樹木の根を介した森林生態系の新たな理解を広めることを目的とする。「樹木の根について知りたい」という読者に応えることが本書のねらいである。
第1章から第3章までは,樹木根の基礎的な仕組みを,太い根や細い根などの機能や構造,成長特性を通して紹介する。第4章では変動する環境下における樹木根の反応を,第5章では根系の発揮する減災機能を取り扱う。終章で樹木根の発揮する生態系サービスをとりまとめ,持続可能な森林や社会への貢献を,樹木の根という視点から解説する。
目次
序章 森林を支える樹木根
第1章 樹木の根系と分布
第2章 樹木根の成長
第3章 物質循環と樹木根
第4章 環境変動と樹木根
第5章 樹木根の発揮する減災機能
終章 樹木根と森林の生態系サービス
著者等紹介
平野恭弘[ヒラノヤスヒロ]
1998年名古屋大学大学院生命農学研究科林学専攻博士課程修了。現在、名古屋大学大学院環境学研究科准教授、博士(農学)。根研究学会会長(2020‐2021)。専門は森林科学・環境学
野口享太郎[ノグチキョウタロウ]
1999年東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻博士課程修了。現在、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所チーム長(根系動態研究担当)、博士(農学)。専門は森林生態学
大橋瑞江[オオハシミズエ]
2000年九州大学大学院農学研究科林業学専攻博士課程修了。現在、兵庫県立大学環境人間学部教授、博士(農学)。専門は森林生態学・生物地球化学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
mft