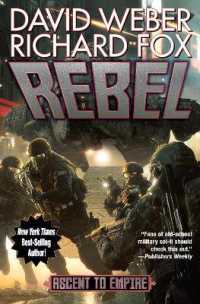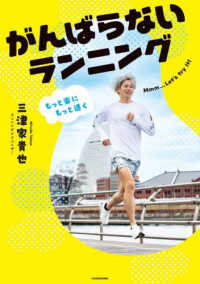出版社内容情報
ルビーレーザーの発明から遅れること50年余りで,ついにX線領域でも実用的なレーザーが実現した。しかも,現在世界に2台しかないX線自由電子レーザーの内1台が日本で稼働している。このSACLAを舞台にして世界中の研究者によってX線領域の非線形光学の研究が開始され,その前線は急速に拡大している。本書では立ち上がりつつあるX線非線形光学という新分野の今を紹介している。
シリーズの思想に沿って,本書は基本的な電磁気学と量子力学といった最小限の予備知識で読破できるように書かれている。一方で専門書であるので本筋の議論は数式を用いて可能な限り誤魔化さずに進めてある。式を追うことで,可視光領域の光学が前提としていた様々な近似が破れるところに,X線特有の現象が現れる様子を見ることができる。またX線の非線形光学は原子物理や光物性そして加速器科学とも境界を接している。これら関係する部分についても簡単な解説を加えて,総合的な理解を助けている。
読者は本書を通じて大学で習っている教科書的な物理学の上にどのようにX線非線形光学が構築されているか俯瞰し,最先端までの距離を感じられるだろう。
第1章 X線の非線形光学
1.1 歴史的なこと
1.2 X線の非線形光学の面白さ
第2章 X線と物質の相互作用の基礎
2.1 電磁波に対する物質の応答
2.1.1 電場とベクトルポテンシャル
2.1.2 電流密度と電場の関係
2.1.3 分極率
2.1.4 非線形な電流の場合
2.2 電流密度の計算
2.2.1 電流密度の表式
2.2.2 時間に依存する摂動
2.2.3 ハミルトニアン
2.2.4 1次摂動を受けた波動関数
2.2.5 線形な電流密度
2.2.6 双極子近似
2.2.7 等方的な場合
2.2.8 吸収と異常分散補正
2.3 2次の非線形性を持つ電流密度
2.3.1 非線形電流を与える行列要素
2.3.2 非線形電流密度の計算例
2.3.3 2次の非線形分極率
2.4 散乱理論
2.4.1 線形過程のファインマン図形
2.4.2 2次の非線形過程のファインマン図形
2.5 古典論との対応
第3章 X線の散乱の基礎
3.1 X線の散乱
3.1.1 ボルン近似の散乱振幅
3.1.2 微分散乱断面積
3.1.3 電子による散乱と古典電子半径
3.1.4 原子による散乱と原子散乱因子
3.2 結晶による散乱
3.2.1 結晶の分極率
3.2.2 格子のフーリエ変換と逆格子
3.2.3 無限に大きい結晶
3.2.4 単位構造のフーリエ変換と結晶構造因子
3.2.5 有限サイズの結晶とラウエ関数
3.2.6 熱振動の効果
3.2.7 格子面と逆格子ベクトル
3.2.8 ダイヤモンド型構造の結晶構造因子
3.3 ダーウィン流のX線回折理論
3.3.1 ブラッグ反射
3.3.2 ダーウィン流の考え方
3.3.3 格子面の反射波
3.3.4 格子面の透過波
3.3.5 結晶の反射率と透過率
3.3.6 一般の結晶の場合
3.3.7 結晶の反射率曲線
3.3.8 ブラッグ反射の幅
3.3.9 全反射
3.4 X線の光学理論
3.4.1 格子面の透過波の位相と屈折率
3.4.2 全反射ミラー
3.4.3 多層膜ミラー
3.5 ラウエ流の動力学的X線回折理論
3.5.1 ミクロなマクスウェルの方程式
3.5.2 波動方程式
3.5.3 結晶中の基本方程式
3.5.4 分極率と感受率と局所場補正
3.5.5 ブラッグ条件から遠い場合
3.5.6 2波近似
3.5.7 2波近似の分散面
3.5.8 複屈折
第4章 基本的なX線光学系
4.1 X 線光源
4.1.1 蓄積リング
4.1.2 X線自由電子レーザー
4.1.3 光源比較
4.2 光学素子
4.2.1 分光器
4.2.2 デュモンド図形
4.2.3 KBミラーによる集光
4.2.4 分光測定
4.3 検出器
4.3.1 フォトダイオード
4.3.2 シンチレーション検出器
4.4 X 線非線形結晶
4.4.1 平面波光学系
4.4.2 ダイヤモンド結晶の評価
第5章 非線形な散乱過程
5.1 3つともX線の場合の2次の非線形分極率
5.1.1 Uの計算
5.1.2 Bの見積り
5.1.3 反転対称性の影響
5.1.4 結晶の2次の非線形分極率
5.1.5 非線形分極率の大きさ
5.2 第2高調波発生
5.2.1 電流密度
5.2.2 第2高調波の波動方程式
5.2.3 運動学的な解
5.2.4 近似的な解
5.2.5 位相整合と非線形回折
5.2.6 動力学的な位相整合の可能性
5.2.7 第2高調波発生の実験
5.3 X線パラメトリック下方変換
5.3.1 X線パラメトリック下方変換の位相整合条件
5.3.2 X線パラメトリック下方変換の実験例
5.3.3 X線パラメトリック下方変換の展開
第6章 長波長領域へのX線パラメトリック下方変換
6.1 回折限界
6.1.1 波長と回折限界
6.1.2 回折限界が与える制限
6.1.3 回折限界を超える方法
6.2 アイドラーが長波長領域の場合の2 次の非線形分極率
6.2.1 U の計算
6.2.2 非線形分極率と局所光学応答
6.3 結合波動方程式
6.3.1 電流密度と波動方程式
6.3.2 パラメトリック下方変換の基本方程式
6.3.3 位相整合の取り方
6.3.4 結合波動方程式の近似解
6.3.5 結合波動方程式の解
6.3.6 実験との比較
6.4 ファノ効果
6.4.1 自動イオン化スペクトル
6.4.2 ファノ効果の量子論
6.4.3 コンプトン散乱とパラメトリック下方変換のファノ効果
6.5 X線非線形感受率の共鳴効果
6.5.1 炭素のK吸収端でのパラメトリック下方変換
6.5.2 規格化されたエネルギーの表式
6.5.3 ロッキングカーブの解析結果
6.5.4 非線形感受率の共鳴効果
6.6 ダイヤモンドの局所光学応答
6.6.1 X 線パラメトリック下方変換の逆格子ベクトル依存性
6.6.2 線形感受率の再構成
6.6.3 ローレンツ模型との比較
6.7 和周波発生の実験
第7章 非線形な吸収過程
7.1 高強度X線と物質との相互作用
7.2 X線吸収の基礎
7.2.1 水素様原子の吸収断面積
7.2.2 吸収端近傍
7.2.3 K殻ホール状態からの緩和
7.2.4 緩和過程のカスケード
7.3 逐次的な2光子吸収
7.3.1 K殻2重イオン化
7.3.2 レート方程式
7.3.3 パルス幅効果
7.3.4 強度揺らぎの効果
7.3.5 クリプトンのK殻2重イオン化実験
7.4 直接2光子吸収
7.4.1 X線の直接2光子吸収断面積
7.4.2 ゲルマニウムの直接2光子吸収実験
7.4.3 電子配置ダイナミクスのシミュレーション
7.4.4 パルスエネルギー依存性の解釈
7.4.5 基底状態の直接2光子吸収分光
7.5 吸収の飽和と増大
7.5.1 可飽和吸収
7.5.2 X線レーザー
7.5.3 共鳴による吸収増大
第8章 X線非線形光学の展望
8.1 既知の未踏領域
8.1.1 "明るい"未来
8.1.2 X線の量子光学
8.1.3 基底状態を測定できる限界
8.1.4 誘導過程が可能な強度
8.1.5 ポンデロモーティブエネルギー
8.1.6 シュウィンガー極限
8.2 真空の非線形光学
8.2.1 光子-光子散乱
第9章 付録
9.1 フーリエ変換
9.1.1 フーリエ変換の定義
9.1.2 畳み込み積分のフーリエ変換
9.1.3 パルス幅とスペクトル幅の関係
9.1.4 線幅と寿命の関係
9.2 単位系について
須藤 彰三[ストウ ショウゾウ]
岡 真[オカ マコト]
玉作 賢治[タマサク ケンジ]
目次
第1章 X線の非線形光学
第2章 X線と物質の相互作用の基礎
第3章 X線の散乱の基礎
第4章 基本的なX線光学系
第5章 非線形な散乱過程
第6章 長波長領域へのX線パラメトリック下方変換
第7章 非線形な吸収過程
第8章 X線非線形光学の展望
付録
著者等紹介
玉作賢治[タマサクケンジ]
1996年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了、博士(工学)。理化学研究所研究員。2005年同専任研究員。2009年科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)(~2013年)。2014年理化学研究所チームリーダー。専門はX線物理(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
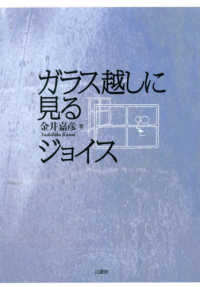
- 和書
- ガラス越しに見るジョイス


![karrimor SPECIAL 2WAY BAG BOOK [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/4299060318.jpg)