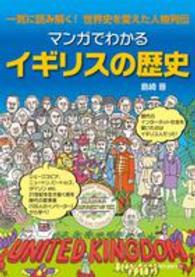出版社内容情報
「コンピュータ」の姿としてよく描かれるキーボードやマウス,ディスプレイ等は,正確にはコンピュータ(電子計算機)ではなく,「インタフェース(デバイス)」と呼ばれる部分にあたる。我々人間とコンピュータの仲立ちをするインタフェースデバイスは,コンピュータの「顔」であるだけでなく,使い勝手を大きく左右する部分でもある。ところが,インタフェースデバイスの製作には,ハードウェア・ソフトウェア・メカ等,多種の技術が必要であり,さらには「使い勝手」を適切に評価する必要もあるなど,障壁となる点が多い。
本書では,読者の方々が「インタフェースデバイス」を作ろうとした際に,どんな手順で,何に注意しながら作っていけば良いかを,実際の製作例を示しながら,順を追って紹介していく。また,現在使われている(あるいは研究されている)代表的なインタフェースデバイスの構造も併せて紹介している。トリビア的な注釈やコラムも多数掲載されているので,肩肘張らずに楽しく読み進めていただけるだろう。
第1章 インタフェースとは何か?
1.1 「万能の箱」との対話
1.2 インタフェース前史:スイッチ&ランプから文字へ
1.3 ハードウェア部分がインタフェースデバイス
1.4 総合力が要求されるインタフェースデバイス製作
1.5 使いやすいマウスを作るには
1.6 最も重要なのは,「良し悪し」の判断ができること
第2章 インタフェースのつくりかた
2.1 ステップ1 ゴールと満たすべき条件を定める
2.2 ステップ2 使用頻度を見極める
2.3 ステップ3 使用環境(および使用者)の明確化
2.4 ステップ4 既存技術の調査
2.5 ステップ5 設計
2.6 ステップ6 実装とブラッシュアップ
第3章 つくってみよう,インタフェース
3.1 ステップ1 ゴールと満たすべき条件を定める:「小さくしても使いにくくならないインタフェース」
3.2 ステップ2&3 頻度・用途・使用環境の明確化:「誰もが日常的に使うもの」
3.3 ステップ4?6 ケース1 常時装用型キーボード:装着しながら生活できるキーボードデバイス
3.4 ステップ4?6 ケース2 常時装用型ハンドセット:ウェアラブルな電話とは?
3.5 本章のまとめ
第4章 インタフェースの仕組み(定番から未来まで)
4.1 キーボード(鍵盤 / Keyboard)
4.2 ポインティングデバイス(Pointing Device)
4.3 ディスプレイ(Display)
4.4 音(Audio / Voice)・触覚(Haptics)・嗅覚(Olfaction)・味覚(Gustation)
4.5 ウェアラブル(Wearable)・ユビキタス(Ubiquitous)
4.6 VR / AR(Virtual Reality / Augmented Reality)
4.7 インタフェースの未来
付録 インタフェース製作の勘どころ五ヶ条(+α)
あとがき
解説(コーディネーター 土井 美和子)
索 引
福本 雅朗[フクモト マサアキ]
土井 美和子[ドイ ミワコ]
目次
1 インタフェースとは何か?(「万能の箱」との対話;インタフェース前史―スイッチ&ランプから文字へ ほか)
2 インタフェースのつくりかた(ゴールと満たすべき条件を定める;使用頻度を見極める ほか)
3 つくってみよう、インタフェース(ゴールと満たすべき条件を定める―「小さくしても使いにくくならないインタフェース」;頻度・用途・使用環境の明確化―「誰もが日常的に使うもの」 ほか)
4 インタフェースの仕組み―定番から未来まで(キーボード;ポインティングデバイス ほか)
付録 インタフェース製作の勘どころ五ヶ条(+α)
著者等紹介
福本雅朗[フクモトマサアキ]
1990年電気通信大学大学院博士前期課程修了。現在、Microsoft Research、Lead Researcher、博士(工学)。専門はヒューマンインタフェースデバイス、ポータブル&ウェアラブルコンピュータ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たいそ