- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
特別支援教育の意義と原理,障害等に応じた子ども理解と支援のあり方,福祉・教育相談・学級経営等への応用について,平易に解説。
特別支援教育コーディネーター必携!
● 詳細目次 ●
【Ⅰ 特別支援教育の原理】
1章 特別支援教育への転換
1.特殊教育と特別支援教育
特殊教育と特別支援教育の違い/転換の背景
2.特別支援教育の実施体制
教師の意識改革/校内支援体制の整備/巡回相談事業の活用/専門家チームとの連携
2章 教育的ニーズの把握とコーディネーション
1.「教育的ニーズ」と「特別な教育的ニーズ」
「指導」「教育」「支援」について/「教育的ニーズ」と「特別な教育的支援」/特別な教育的ニーズの把握
2.教育と他の専門機関との連携
児童生徒のライフステージと専門機関との関係/連携の実際
3章 軽度発達障害児の医学
1.軽度発達障害について
「軽度」の意味/「発達障害」とは/「軽度発達障害」とは
2.AD/HD
AD/HD概論/AD/HDの診断/AD/HDの治療・対処
3.高機能自閉症
自閉症概論/「高機能」とは/アスペルガー障害の診断
Q&A 個別の教育支援計画は誰が作成し,どのような内容が盛り込まれるのですか? 個別の指導計画とはどのような違いがあるのですか?
Q&A 特別支援教育の体制では,従来の特殊学級や盲・聾・養護学校はどのようなかたちに変わっていくのですか?
Q&A 教育,医療,福祉,労働の専門機関の連携において重要なことはどんなことですか?
Q&A 特別支援教育の対象は,軽度発達障害に含まれるAD/HD・LD・高機能自閉症の三つだけですか?
【Ⅱ 特別支援教育の子ども理解】
4章 障害乳幼児の理解と親支援
1.保護者等への支援
早期の支援/障害の受容/家族への支援/情報提供
2.障害乳幼児への支援
障害乳幼児の支援における配慮の基本/障害種別に対応した専門的な支援の内容
3.幼稚園や保育所における障害児保育への配慮
幼稚園や保育所の保育体制と保護者支援/集団生活への適応
5章 発達障害児の理解と支援
1.発達障害の相互関連
発達障害の特徴/出現率
2.LDの理解と支援
LD概論/LDの特徴/LD児の支援例
3.知的障害児の理解と支援
知的障害概論/知的障害の特徴
4.支援の一般的原則
6章 運動障害児の理解と支援
1.運動障害とは
運動障害の定義/運動障害の範囲と程度/運動障害の起因疾患
2.運動障害児の教育
学校教育の場/就学基準/学校数,学級数及び児童生徒数/教育課程/自立活動/卒業後の進路/運動障害児への支援のポイント
7章 聴覚障害児の理解と支援
1.聴覚障害とそれがもたらす種々の影響について
聴覚障害は見えない障害/聴覚障害は社会的関係の障害――人や社会からの疎外状況の大きさ/耳の働きと聞こえの障害/聞こえの状況や補聴効果は簡単にはわからない
2.聴覚障害児の教育と支援
「ことばの遅れ」だけが問題ではない/早期聴覚活用から「前言語からのコミュニケーション保障」へ/手話の導入とろうバイリンガル教育への動向/なぜ日本手話なのか/手話コミュニケーションをベースにした日本語教育
8章 病弱児の理解と支援
1.病弱とはなにか
2.生活規制の難しさについて
生活規制の難しさの分析/生活の変更・維持の支援
3.自分の病状を知る難しさについて
病状変化を認識する難しさの分析/病状変化の認識を促す支援
4.年齢とともに変わる病気とのかかわりについて
幼児期/学童期/思春期・青年期/病弱児独自の心理発達などない
5.教育的支援のポイントについて
意味の世界へ/病気への対処方略を共に考える
6.特別支援教育の中の病弱教育
「いっしょに暮らす」と「同じに暮らす」の違い/「ニーズ」の掘り起こし
9章 視覚障害児・者の理解と支援
1.視覚障害児・者とは
視覚障害児の発達の可能性/中途視覚障害者の心理と理解
2.視覚障害児・者の潜在能力の開発
視覚障害の程度と教育/触知覚による図形認識
3.触知覚能力を高める指導
ノイズに対する抵抗性を強めるには/学習効果の転移度を高めるには/幼児期から触察経験を豊かに
4.視覚障害児と教育形態
視覚障害児と盲学校/視覚障害児の統合教育/視覚障害児のニーズと教育形態
10章 コミュニケーション障害児の理解と支援
1.はじめに
2.“ことば”とその障害
3.“ことば”と概念
4.豊かなコミュニケーションに向けて
Q&A 幼稚園や保育所に在園している障害児の実態はどのようになっていますか?
Q&A 発達障害の子どもたちが社会に適応し,就職できるようになるためには,どのような支援が必要ですか?
Q&A 現在の医療的ケアの動きはどのようになっていますか?
Q&A 聞き取りや発音が十分でないのは仕方ないとも思いますが,読み書きの力や教科学習の力だけは付けさせたいです。どのような指導が必要でしょうか?
Q&A 幼稚園に通っている男児です。2歳半頃から「ぼ・ぼ・ぼ・ぼく……」というように,うまく言葉が出てきません。どうすればよいでしょうか?
Q&A 高次脳機能障害とはどのような障害ですか?
【Ⅲ 特別支援教育の応用】
11章 障害児・者の福祉と支援
1.はじめに
2.手帳・手当・年金
手帳/手当/年金
3.補装具と日常生活用具
補装具/日常生活用具
4.医療費の助成
育成医療/更生医療/慢性疾患や難病医療費助成
5.日常生活の援助
心身障害児・者の居宅介護等事業
6.施設,訓練
施設/児童デイサービス事業・訓練事業
12章 子どもの困難状況の理解と支援
1.困難状況を的確にとらえ,適切な支援を行うことの大切さ
何気ない“不条理な”励まし/気づかないうちに生じている(生じさせている)困難/子どもの行動をとらえる視点
2.困難が生じる背景
困難状況はどうやって生じるか/「障害」の機能モデル,相互作用モデル/さまざまな背景,機序を考える
3.困難状況を理解するとは
困難状況の“構図”をとらえる/多様な場面を考慮する
4.支援を考える
違いを見いだす/“構図”をつくり変える手段を探す
5.支援を考える際に考慮すべきいくつかの点
認知的負荷を減らす/必然性の必要性(要求されていないことは学ばない)/保護者との関係を築く
13章 個別の教育支援計画・指導計画と実践記録
1.情報提供と共通理解のためのシステム
2.計画の作成と活用
作成作業の前に行うべきこと/実態の把握/目標の設定/具体的な支援内容/活用と評価
3.記録の集積と分析
時間の壁と要因の複雑さ/コンピュータの活用/画像の利用/“主観”の大切さとデータによる補完
4.情報の共有――実態把握と支援・指導のリソース
14章 学校適応と教師のカウンセリングマインド
1.学校適応をめぐる問題と背景
不登校やいじめの実態/学校適応に影響する背景的要因/教育相談の取り組み
2.カウンセリング
カウンセリングの考え方/教師とカウンセラーの専門性/指導的アプローチとカウンセリング的アプローチ
3.支援の実際
実際の対応方法/取り組みにおける基本的視点
15章 特別支援教育の学級経営
1.学級経営の方針
学級崩壊/学級経営の基本方針/人権の教育
2.集団づくり
周囲の子どもたちにどう伝えるか/違いを認め合う集団づくりの例
16章 特別支援教育コーディネーターの実際
1.特別支援教育コーディネーターの役割と資質
コーディネーターの役割/コーディネーターの配置と資質
2.コーディネーターの実際
保護者との関係調整/校内の関係調整/関係機関との連携
Q&A 「不登校」は,どうして中学生に多いのですか?
Q&A 通常学級に1学年以上の学力が遅れている子どもが在籍しています。授業ではどのような支援をしたらいいですか?
Q&A 特別支援教育コーディネーターに指名されました。校内では何から取り組めばいいのですか?保護者とはどのようにして信頼関係を築いたらよいのですか?
内容説明
本書は特別支援教育に関する入門テキストとして編集したもので、宮城教育大学の特別支援教育総合研究センターの設立を機に、障害児教育講座及び関連する講座・センターのスタッフの総力をあげて作成に当たったものである。
目次
1 特別支援教育の原理(特別支援教育への転換;教育的ニーズの把握とコーディネーション;軽度発達障害児の医学)
2 特別支援教育の子ども理解(障害乳幼児の理解と親支援;発達障害児の理解と支援;運動障害児の理解と支援 ほか)
3 特別支援教育の応用(障害児・者の福祉と支援;子どもの困難状況の理解と支援;個別の教育支援計画・指導計画と実践記録 ほか)
著者等紹介
渡辺徹[ワタナベトオル]
宮城教育大学特別支援教育総合研究センター長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
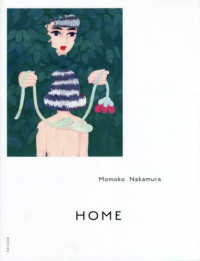
- 和書
- HOME






