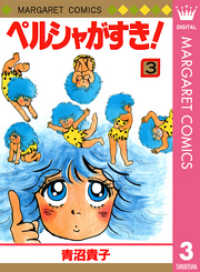内容説明
教育改善を目指す米国の研究者たちは、日本の学校教育・教員研修に活路を見いだした。日・米・独の数学授業ビデオ分析による国際比較研究。
目次
第1章 学習指導のギャップ
第2章 ドイツ・日本・米国の学習指導を研究するための方法
第3章 学習指導のイメージ
第4章イメージの数量的検討
第5章 システムとしての学習指導
第6章 文化的営みとしての学習指導
第7章 米国的改革を超えて:学習指導の日本流改善方式
第8章 持続的改善に向けた舞台設定
第9章 学習指導改善の着実な取り組み
第10章 学習指導という正真正銘の専門職
著者等紹介
スティグラー,ジェームズ・W.[スティグラー,ジェームズW.][Stigler,James W.]
カリフォルニア大学ロサンゼルス校心理学教授。第3回国際数学・理科教育調査ビデオ研究代表者。LessonLab教育研究所の創設者、現所長。1982年ミシガン大学で発達心理学の研究により博士号を取得。1989年グッゲンハイム特別会員となる。1995年全米教師協会のクエスト賞をはじめ、多数の賞を受賞。授業の研究では米国の第一人者
ヒーバート,ジェームズ[ヒーバート,ジェームズ][Hiebert,James]
デラウェア大学教育学教授。第3回国際数学・理科教育調査ビデオ研究数学授業分析の代表。1979年ウィスコンシン大学で教科教育学研究により博士号を取得。全米科学アカデミー(1998・99年度理事)会員。「認知と指導」「数学的な考え方と学習」等の編集委員。2000年にはスウェーデン国立教育センター、並びに同国文部省のコンサルタントをつとめる
湊三郎[ミナトサブロウ]
秋田大学名誉教授。日本数学教育学会(元理事・幹事)、日本教科教育学会(現理事)会員。「数学教育学論究」編集幹事。教科書『小学算数』『中学数学』(教育出版)の共著者。世界的研究誌に論文が掲載された最初の日本人数学教育研究者。1999年第81回全国算数・数学教育研究(秋田)大会実行委員長。現在、秋田県算数・数学教育研究会会長。近年「あきた算数・数学フェスティバル」開催の実行委員長として地域社会の数学教育の発展にも力を注いでいる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。