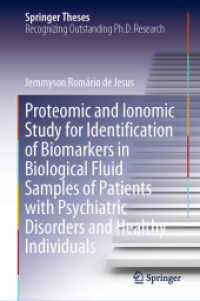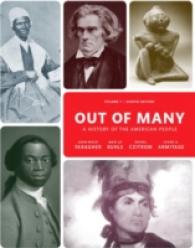出版社内容情報
※【試し読み】はこちら(PDF 5,668KB)
音が脳をつくり、脳が音をつくる。
言葉、音楽、都市の騒音、大自然の静寂、愛する人の声。聴覚は常にオンになっていて、私たちは音から逃げることはできない。人はみな生まれた時から、音と意味を結びつける経験を幾度となく重ね、音と脳の協調関係――独自の《サウンドマインド》――を磨き上げている。
言語障害、自閉症、難聴、バイリンガル、加齢や脳震盪、音楽療法……聞くことは、感じ、考え、動くことにどう影響するのだろうか? 音の持つ力と可能性を説く、聴覚神経科学のトップサイエンティストの集大成。ルネ・フレミング、ミッキー・ハート、ザキール・フセインら世界的ミュージシャンも絶賛!
「聞いた音がどのように私たちを形作るのかについての、 最も美しく、刺激的で、
啓発的な本のひとつ。永遠に読んでいたかった」
――メアリアン・ウルフ(『プルーストとイカ――読書は脳をどのように変えるのか?』著者)
2022年 米国出版協会 専門学術出版賞(生物医学)、ノーチラス・ブック・アワード金賞(科学・宇宙)受賞作。
《トピック》
音楽家の脳/音のリズムと脳のリズム/リズムと社会化/音と「読む脳」/自閉症/言語障害に性差はあるか?/音楽療法/バイリンガルの脳/貧困と言語環境/鳥のさえずりは言語か、音楽か?/「安全な」騒音の影響/聴覚の老化を食い止める/スポーツにおける脳震盪 ほか
内容説明
言葉、音楽、都市の騒音、大自然の静寂、愛する人の声―聞くことは、感じ、考え、動くことにどう影響するのだろうか?音の持つ力と可能性を説く、聴覚神経科学のトップサイエンティストの集大成。ルネ・フレミングら世界的ミュージシャンも絶賛!2022年米国出版協会専門学術出版賞(生物医学)/ノーチラス・ブック・アワード金賞(科学・宇宙)。
目次
サウンドマインド―音と脳の協調関係
第1部 音の働き(頭の外の信号;頭の中の信号;学習―頭の外の信号が頭の中の信号に変わるとき;聴く脳―探究)
第2部 音は私たちを形作る(音楽はジャックポット―感覚・思考・運動・感情の大当たり;頭の中のリズム、頭の外のリズム;言語のルーツは音;音楽と言語の協調関係;バイリンガル脳 ほか)
著者等紹介
クラウス,ニーナ[クラウス,ニーナ] [Kraus,Nina]
Ph.D.神経科学者。ノースウェスタン大学コミュニケーション科学・障害学部教授。ピアニストの母の影響で幼少期から音楽に親しむ。成人の神経系が学習後に再編成される可能性を最初に示した研究者の一人。30年にわたり音処理の生物学的基礎についての先駆的な研究を行ない、世界で上位1%とされるResearch.comベストサイエンティストの神経科学分野にランクインしている
柏野牧夫[カシノマキオ]
日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所柏野多様脳特別研究室長。NTTフェロー。人間の認知や行動の多様性について、脳・身体・環境の相互作用の観点から研究。2016年に「多様な環境での柔軟な知覚を支える人間の聴覚機構の研究」で文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞
伊藤陽子[イトウヨウコ]
翻訳家。東京女子大学文理学部心理学科卒。翻訳を柴田裕之氏に師事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
takka@ゲーム×読書×映画×音楽
kirinsantoasobo
やいっち
MASA123