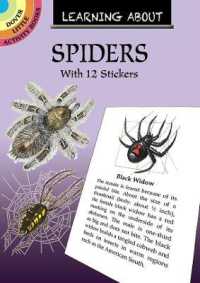出版社内容情報
★NHK「ひるまえほっと」の「中江有里のブックレビュー」コーナーで紹介(2022年1月11日放送)!
★「日本経済新聞」(2022年1月8日)、「毎日新聞」(1月15日)に書評掲載!
真の「幸福」とは
携帯電話、パソコン、テレビ、洗濯機、電動工具、時計、ガスコンロ、蛇口の水も、いっさいない暮らしがはじまった。究極の生活から見えてきたのは――
『ぼくはお金を使わずに生きることにした』著者の新たな挑戦!
3年間お金なしで暮らした著者が、今度は電気や化石燃料で動く文明の利器をいっさい使わずに、仲間と建てた小屋で自給自足の生活をはじめた。火をおこし、泉の水を汲み、人糞堆肥で野菜を育て、鹿を解体して命を丸ごと自分の中に取りこむ。地域の生態系と調和した贈与経済の中で暮らす1年を、詩情豊かに綴る。
アイリッシュ・インディペンデント紙「ブック・オブ・ザ・イヤー2019」
<本書より>
明日から小屋で電気のない生活――長いあいだ当然視してきた文明の利器、すなわち電話、コンピューター、電球、洗濯機、蛇口の水、テレビ、電動工具、ガスコンロ、ラジオも、一切ない暮らし――がはじまるという日の午後、一通の電子メールが届いた。ぼくが受けとる人生最後のメールとなるかもしれない。差出人は出版社の編集者だった。その日の新聞に寄稿した文章を読んで、体験をもとに本を書く気はないかと連絡をくれたのだ。
二〇代はじめの自分をふりかえると、自尊心の源はおもに「どれだけ多くカネをかせいだか」であった。最近では「必要とするカネがどれだけ少ないか」が自尊心の源になっていることに気づく。
丸一日の休みを最後にとったのは、いつだろう。こういう暮らしでは、何もせずふとんにくるまって過ごす一日など、命にかかわりかねない。ひねるだけの蛇口、押すだけのボタン、タイマー設定するだけのセントラルヒーティング、気軽に立ち寄れるカフェ、一日じゅうのんびりさせてくれるスイッチ類など、そうした便利なものは何ひとつありはしない。つねに、例外なく、何かしらすべき仕事がある。
裏返せば、ほぼ毎日、生きている実感をおぼえるということだ。
ピーナッツバター、バナナ、天日干しのドライトマトなど、アイルランドでは自給不可能なごちそうを懐かしく思うときもあるが、それもごくたまにの話だ。それに、広い世界でたとえどんな危機や大変動が起きようとも、自分自身や隣人や愛する人のための食卓をととのえる方法を知っていれば、本物の安心感が得られる。
健康のための時間をつくらずにいると、病気のための時間をつくるはめにおちいる。
自然の猛威を感じとりたい。よけいな物をはぎ取ったあとに残る本質を味わいつくしたい。本物の親密さを、友情を、コミュニティを知りたい。真実を探求して、そんなものが実際に存在するのかどうか確かめたい。たとえ存在しなかったとしても、少なくともぼくにとっての真実に近いものを見つけたい。寒さや飢えや恐れを感じたい。単に生命を維持するだけでなく、生きている実感を持って生きたい。そして、そのときが来たら、あわてず騒がず森へ行き、森の生物たちにぼくの肉体を食べさせてやる心づもりをしておきたい。
【目次】
著者より
プロローグ
自分の場所を知る
冬
春
夏
秋
シンプルであることの複雑さ
後記
無料宿泊所〈ハッピー・ピッグ〉について
【著者】マーク・ボイル(Mark Boyle)
1979年、アイルランド生まれ。大学でビジネスを学んだ後、渡英。29歳からの3年間、まったくお金を使わずに暮らした。現在は、アイルランド西部のゴールウェイ県にある小農場に自ら建てた小屋で、近代的テクノロジーを使わない自給自足の生活を送っている。農場の敷地内で、無料の宿泊所兼イベントスペース〈ハッピー・ピッグ〉もいとなむ。
著書『ぼくはお金を使わずに生きることにした』は20以上の言語に翻訳され、日本でも大きな反響を呼んだ。他の著書に、『無銭経済宣言――お金を使わずに生きる方法』(以上、紀伊國屋書店)、『モロトフ・カクテルをガンディーと――平和主義者のための暴力論』(ころから)がある。
【訳者】吉田奈緒子(よしだ・なおこ)
1968年、神奈川県生まれ。東京外国語大学インド・パーキスターン語学科卒。英国エセックス大学修士課程(社会言語学)修了。千葉・南房総で「半農半翻訳」の生活を送り、蛇腹楽器コンサーティーナでアイルランド音楽を弾く。訳書に、ボイル『ぼくはお金を使わずに生きることにした』、サンディーン『スエロは洞窟で暮らすことにした』(以上、紀伊國屋書店)など。
内容説明
三年間お金なしで暮らした著者が、今度は電気や化石燃料で動く文明の利器を一切使わずに、仲間と建てた小屋で自給自足の生活をすることにした。火をおこし、泉の水を汲み、人糞堆肥で野菜を育て、鹿を解体して命を丸ごと自分の中にとりこむ。地域の生態系と調和した贈与経済の中で暮らす一年を、詩情豊かに綴る。
目次
自分の場所を知る
冬
春
夏
秋
シンプルであることの複雑さ
著者等紹介
ボイル,マーク[ボイル,マーク] [Boyle,Mark]
1979年、アイルランド生まれ。大学でビジネスを学んだ後、渡英。二九歳からの三年間、まったくお金を使わずに暮らした。現在は、アイルランド西部のゴールウェイ県にある小農場に自ら建てた小屋で、近代的テクノロジーを使わない自給自足の生活を送っている。農場の敷地内で、無料の宿泊所兼イベントスペース“ハッピー・ピッグ”もいとなむ
吉田奈緒子[ヨシダナオコ]
1968年、神奈川県生まれ。東京外国語大学インド・パーキスターン語学科卒。英国エセックス大学修士課程(社会言語学)修了。千葉・南房総で「半農半翻訳」の生活を送り、蛇腹楽器コンサーティーナでアイルランド音楽を弾く(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
M
ちょび
くさてる
ykshzk(虎猫図案房)
-

- 電子書籍
- 追放皇子の帝位奪還(9) サイコミ×裏…
-
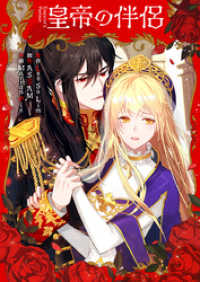
- 電子書籍
- 皇帝の伴侶【タテヨミ】第43話 pic…