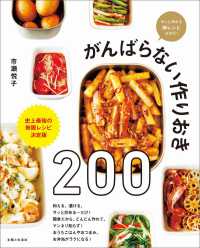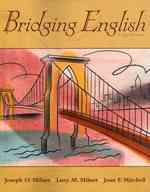出版社内容情報
イラク戦争から10年、いま問われることとは―
1831年にトクヴィルが描いた アメリカ人像は総じて対外戦争を忌避する「平和愛好者」だった。しかし以後のアメリカは対インディアン闘争や外国への軍事介入などを繰り返し、国外での軍事力の行使は第二次大戦以降だけでも150回に及ぶ。
本書では、国民が開戦を受け容れてきた歴史をたどり、開戦事由の欺瞞を衝くとともに、アメリカ人特有の市民宗教ともいうべき愛国心観、共同体意識、孤高のヒーロー像をあぶりだし、さらには反戦運動の系譜から、著者自身の専門である「紛争解決」の歴史・実績と採用の推奨へと結ぶ。イラク戦争開戦から10年、アメリカ対外戦争を是認し追随してきた日本で、あらためて読まれるべき硬質なアメリカ論。
目次
はじめに
第1章 なぜ、私たちは戦争を選ぶのか
第2章 自衛の変質
第3章 悪魔を倒せ―人道的介入と道徳的十字軍
第4章 「愛せよ、しからずんば去れ」―愛国者と反対者
第5章 戦争は最後の手段か?―和平プロセスと国家の名誉
おわりに より明確に戦争を考察するための五つの方法
リチャ-ド・E・ル-ベンスタイン
1938年生まれ。ジョージ・メイソン大学教授。国際紛争解決が専門「パブリッシャーズ・ウィークリー」誌の最優秀宗教書に選ばれたWhen Jesus Became God(未邦訳)のほか、著書に「中世の覚醒―アリストテレス再発見から知の革命へ」(紀伊國屋書店)
小沢千重子
1951年東京生まれ。東京大学農学部卒。現在ノンフィクション分野の翻訳に従事している。訳書にルーベンスタイン「中世の覚醒」、アンサーリー「イスラームから見た『世界史』、クロスビー「数量化革命」「飛び道具の人類史」、デントン「動物の意識 人間の意識」(共訳)、ローズ「原爆から水爆へ」(共訳、いずれも紀伊國屋書店)ほかがある。
内容説明
愛国心・共同体意識・孤高のヒーロー像・自衛の概念・開戦事由のレトリック―戦争が常態化する国アメリカの歴史から集団暴力が道徳的に正当化されてきた文化・社会的要因を探る。
目次
第1章 ―なぜ、私たちは戦争を選ぶのか(ビリー・バッド症候群と政府当局による欺瞞の記録;ビリー・バッドではなくディヴィー・クロケットなのか?開拓地の戦士仮説 ほか)
第2章 自衛の変質(国内制度の防衛―第一次セミノール戦争;普遍的な価値と国家の独立の防衛―両次の世界大戦 ほか)
第3章 悪魔を倒せ―人道的介入と道徳的十字軍(サッダーム・フセインの悪魔化;悪魔のような敵の基本的な属性 ほか)
第4章 「愛せよ、しからずんば去れ」―愛国者と反対者(愛国心とアメリカの共同体主義;反戦論者と体制からの離脱者―ベトナム以前の反戦運動 ほか)
第5章 戦争は最後の手段か?平和プロセスと国家の名誉(雄々しい戦争と女々しい交渉;「最後の手段」としての戦争、およびそのほかの民間伝承 ほか)
著者等紹介
ルーベンスタイン,リチャード・E.[ルーベンスタイン,リチャードE.] [Rubenstein,Richard E.]
1938年生まれ。米国ジョージ・メイソン大学教授。国際紛争解決が専門
小沢千重子[オザワチエコ]
1951年生まれ。東京大学農学部卒。ノンフィクション分野の翻訳に従事している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
Mizhology
pyonko
gq550_tomy
じろ
-
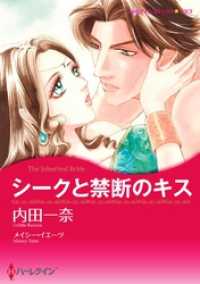
- 電子書籍
- シークと禁断のキス【分冊】 8巻 ハー…