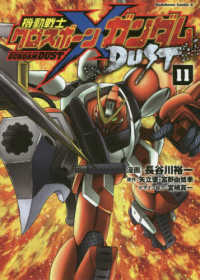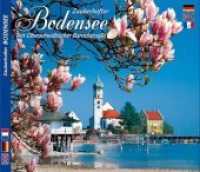出版社内容情報
量子力学をめぐる哲学的問題を、物理学および科学哲学の世界的権威である著者が、歴史的展望の上に立って総括的にまとめた力作。
第1章 形式と解釈
1.1 形式
1.2 解釈
第1章への註
第2章 初期の半古典的解釈
2.1 1926/1927年間の着想をめぐる情況
2.2 Schrodingerの電磁的解釈
2.3 流体力学的解釈
2.4 Bornの最初の確率的解釈
2.5 De Broglieの2重解による解釈
2.6 最近の半古典的解釈
第2章への註
第3章 不確定性関係
3.1 不確定性関係の初期の歴史
3.2 Heisenbergの推論
3.3 その後の不確定性関係の導出
3.4 哲学的な意味合い
3.5 その後の諸発展
第3章への註
第4章 初期の相補性解釈の説明
4.1 BohrのComo講演
4.2 批判的注意
4.3 ”平行的”相補性と”循環的”相補性
4.4 歴史上の先行者達
第4章への註
第5章 Bohr-Einstein論争
5.1 第5回Solvay会議
5.2 初期のBohrとEinsteinとの間の討論
5.3 第6回Solvay会議
5.4 光子箱の実験ならびに時間-ネネルギー
不確定関係式をめぐるその後の議論
5.5 Bohr-Einstein論争の評価
第5章への註
第6章 不完全性の反論と後期の相補性解釈の説明
6.1 ミクロ物理学的属性の相互作用による把握
6.2 EPRの議論の前史
6.3 EPRの不完全性の議論
6.4 EPRの議論に対する初期の反応
6.5 量子状態の関係的な把握
6.6 数学的な仕上げ
6.7 EPRの議論に対するその後の反応
6.8 相補性解釈の受け入れ
第6章への註
マックス・ヤンマー:1915年生まれ。ヘブライ大学およびハーヴァード大学で物理学、科学哲学、科学史を学ぶ。ハーヴァード大学、ボストン大学で教鞭をとった後、コロンビア大学等の客員教授。2007年アメリカ物理学会のAbraham Pais物理学史賞を受賞。
井上 健:1921年大阪に生まれる。1941年京都大学理学部卒。京都大学名誉教授。2004年没。著書に『物理学のすすめ』(筑摩書房)他。
内容説明
本書は、現代物理学および科学哲学の世界的権威である著者が、量子力学をめぐる哲学的問題を、広い歴史的見地から、総括的に解説したものである。著者は、この本をまとめるに当たって、この分野における世界の指導的理論家多数と討論を交しており、その意味から、本書は、このテーマに関して最高の水準で書かれているといえよう。
目次
第1章 形式と解釈
第2章 初期の半古典的解釈
第3章 不確定性関係
第4章 初期の相補性解釈の説明
第5章 Bohr‐Einstein論争
第6章 不完全性の反論と後期の相補性解釈の説明
著者等紹介
ヤンマー,マックス[ヤンマー,マックス][Jammer,Max]
1915年ベルリンに生まれる。ヘブライ大学およびハーヴァード大学で物理学、科学哲学、科学史を学ぶ。実験分子工学でPh.D.取得。ハーヴァード大学、オクラホマ大学、ボストン大学で教鞭をとった後、イスラエルのバル‐イラン大学で物理学教室主任、後に学長に就任。テルアビブ大学の科学史・哲学研究所の共同設立人でもある。スイス連邦工科大学、ゲッテインゲン大学、コロンビア大学等の客員教授。いくつもの社会アカデミー、科学アカデミーの会員で、物理学、哲学の方面で幅広い活動を展開している。アメリカアカデミー芸術・科学研究賞を受賞。2007年、アメリカ物理学会のAbraham Pais物理学史賞を受賞
井上健[イノウエタケシ]
1921年大阪に生まれる。1941年京都大学理学部卒。京都大学名誉教授。2004年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hhhhhhaaaaaa2
-

- 電子書籍
- 私たちが恋する理由【単話】Reason…
-
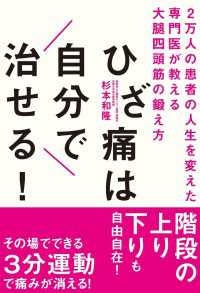
- 電子書籍
- ひざ痛は自分で治せる!