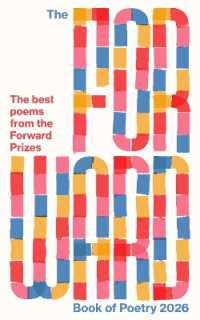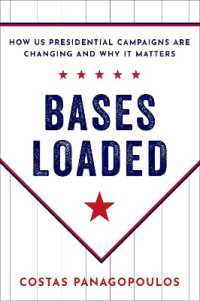出版社内容情報
われわれが考える言語的・分析的な知とは別に,非言語的で包括的なもうひとつの知がある。それが本書でいう「暗黙の知」である。本書は,この暗黙知がコミュニケーションや技能の習得だけでなく,創造的な科学活動において重要なことを説き,従来の通説に反駁する。今まで光を当てられなかった非言語的な知の構造を明らかにし,人間と科学の本質を問い返す。
ポラニーにとって「暗黙知」とは、余人が見落としてきた重要な問題に気づく能力である。解は手順を踏めば得られるが、解くに値する問題を見つけるのは難しい。大切なのは想像力であり、存在する物に対する想いである。端正な文章の背後にある詩情を感じ取りたい。
*******************
われわれが考える知以外に、もうひとつの知がある。
言語的・分析的な知に対する非言語的・包括的な知、それが本書でいう「暗黙知」である。
人間はこれら両方の知を駆使して、ものごとを知覚し、学習し、行動する。
人の顔を識別し、コミュニケーションを交わし、スポーツや技能を体得できるのも暗黙知が働いているからである。
さらに科学においても、この非言語的な知は重要な働きをする。
たとえば問題の所在を知るとか、何かを発見するといった創造的な活動の源となるものである、という。
本書は、今まで光を当てられなかった非言語的な知の構造を明らかにし、人間と科学の本質を問い返す。
また生命現象や科学と社会のあり方にも言及し、
認識論、科学論から哲学の根本問題にわたって再検討を迫る問題の書である。
本書について
本書は小著ながら、知識の理論、科学論から、自然哲学、人間論、近代文明論にまで及ぶ
広範な領域の問題が有機的な関連をもって論じられている点で、重要な意義をもつ著作である。・・・
本書では、暗黙知という非言語的な認識が、はたして存在するかどうかという問題以外にも多くの問題が提起されている。
それを以下に列記してみよう。今後の論議が期待される。
(1)暗黙知の説から、ポラニーは科学において非言語的・包括的な認識が重要であると説いた。
彼は直感という言葉を使っていないが、暗黙知と直感の相違点は何か。
(2)暗黙知の説は、科学が言語的・分析的・合理的な認識にもとづくという従来の通説を批判し、
非言語的な認識の重要性を強調しているが、その妥当性はどうか。
(3)今まで科学の目的は、主観を排した客観的な知を確立することにあるとされてきたが、
ポラニーはこれを批判し、主体的な関与を強調する。この点はどう考えたらいいのか。
(4)創発という概念によって、還元主義を批判し、それぞれのレベルが
下位のレベルには見られない特性をもって階層構造をなしていると考え、
そのような視点から機械、生物、人間、そして社会までもとらえようとしているが、その妥当性はどうか。
また近代進化論をこの創発の立場にもとづいて批判しており、その当否も問題となるだろう。
(5)暗黙知は、ほかの生物や機械に見られぬ人間固有の能力か。
(6)科学論の問題としては、クーンの「パラダイム論」との関係、ポパーの説との関係などが重要な問題となるが、
ポラニーが今日ほとんど顧みられていない実在論の立場から解決を試みていることも注目され、
パラダイム論に関して是非とも考慮されるべき問題である。
(7)ポラニーの階層の概念はさらに厳密な検討が望まれ、とくに社会へのその適応については、
マルクスやパーソンズによる社会構造の把握などとも関連させて検討されてよいであろう。
なお、組織一般の構造的変動については、最近のシステム論や非平衡熱力学などでも
さかんに研究されており、これらの努力と一体となった階層構造とその変動の解明が望まれる。
・・・・
こうしたポラニーの主張は、欧米では広くさまざまな分野で取り上げられていることを強調しておきたい。
訳者あとがき より
*******************
序 (伊東俊太郎)
Ⅰ 暗黙の知
Ⅱ 創 発
Ⅲ 探求者たちの社会
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にいたけ
greenman
rigmarole
takao
あゆさわ