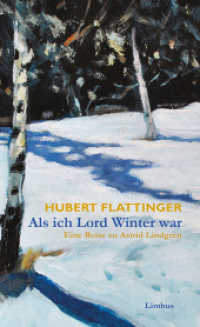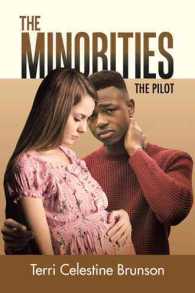内容説明
すぐに始められることはたった1つ。子どもたちと“ぶつかる指導”をやめること。
目次
第1章 荒れを感じるクラスと向き合うために始めること
第2章 子どもが素直に受け入れる叱り方を工夫していこう!
第3章 学習環境を整えてクラスに落ち着きを取り戻そう!
第4章 荒れにつながる言動はこのように改善していこう!
第5章 授業中の「困った」はこのように改善していこう!
第6章 理解と協力を得られる保護者対応をしよう!
著者等紹介
城ヶ崎滋雄[ジョウガサキシゲオ]
1957年、鹿児島県生まれ。1980年、順天堂大学卒業後、千葉県の公立小学校教諭となる。20歳代では、教育委員会に出向し社会教育に携わる。30歳代では、不登校対策教員として不登校児童と関わる。40歳代では、荒れたクラスの立て直しに努める。50歳代では、子育て経験を生かして家庭教育にも活動を広げる。現役の小学校教師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
あべし
4
この本から学べたことは二つあります。 ① システム化 授業が終わったら、次の授業の準備をしてから休み時間にする。教室にゴミが落ちていたら、授業終了前にゴミを拾う指示を出す。 このようにシステム化していくことで、教師がいちいち声をかける必要がなくなり、自治的な集団に近づくと思いました。 ② 友だち力 何か機会を与えないと、子どもたちの人間関係は固まったままです。教師は、そういった機会を子どもたちに与える役割があると思いました。 結局、自分の考えと違う経験が少ないから口論や喧嘩になるのだと思います。2022/11/20
taku
2
学級にちょっとしたほころびが出てきたときにどう対処したらよいかを項目立てて具体的に解説。 三行日記やペア整列など新たに実践してみたいことがあった。2020/07/24
Naoki Shibata
2
生徒とぶつかる前にできることがある!まずは、一歩ひいて受け入れるところからはじめたい。2013/09/15
Mr.Y
0
魔の11月が迫る中、荒れに向き合う手立てを求めて再読。学級が上手くいかなくなってきた職員は本を手に取る気力もなくなる。でも、この本であれば、コンパクトに学級経営を見直すポイントが示されており短時間で読み進めることができる。2016/10/29
Musica
0
荒れという言葉にこの本を選んだのでしょう。保護者の心をほぐす電話連絡の始めが「良いことがありましたよ。」なんだ。やってみよう。2015/12/30