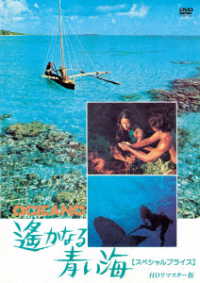目次
1 フィールドワークと文化人類学―人類学者はどのように調査を進めるのか?
2 民族と国家―集団意識はどのように生まれるのか?
3 家族と親族―親と子は血のつながっているものか?
4 セクシュアリティとジェンダー―「性」の多義性とは?
5 交換と経済―他者とは何か?
6 儀礼と分類―人はどのように人生を区切るのか?
7 宗教と呪術―世界は脱魔術化されるのか?
8 死と葬儀―死者はどのように扱われるのか?
9 文化とアイデンティティ―先住民族は消滅するのか?
10 グローバル化と他者―今日のフィールドワークとは?
11 霊長類と文化―霊長類は私たちの文化について何を教えてくれるか?
著者等紹介
奥野克巳[オクノカツミ]
桜美林大学リベラルアーツ学群教授
花渕馨也[ハナブチケイヤ]
北海道医療大学大学教育開発センター准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
★★★★★
5
若手研究者を中心に執筆された文化人類学の入門書。親族関係や儀礼といった、わりとオーソドックスなトピックが、昨今のグローバルな世界情勢を意識した立ち位置から記述されています。理論の紹介だけでなく、執筆者それぞれのフィールドワーク経験を記述する節が各章に設けられている点が特徴的でしょうか。初調査の瑞々さを仮想体験できるような趣向になっています。全体として良書だと思いました。2012/04/02
だちょう
0
様々なトピックから文化人類学が語られる初心者向けの本。我々が当然だと思っている親子関係や、性や宗教が、地域や時代や科学技術の発展で変わっていくものだということがわかって面白い。他者や自文化を色眼鏡をかけずに「知る」ということは難しいものだなと思う。面白かったのは、病院で病気が治らないと呪術師の元に行って相談する民族の話。呪術師に相談して病気を呪術の結果とすることで、病気という体験に折り合いをつけるというのは、近代医療がカバーできなかった人たちが代替医療にすがる現代の日本にも共通するものがあるなあと思った。2017/11/21
ねぎとろくん
0
地球には190以上の国と6,000種以上の言語。 "未開民族"と呼ばれる民族たちは、敢えて"未開"を演じて商業化しているケースも多く、もはや我々の想像する"未開文化"は存在しないというジレンマ。金品授受をせず、相手をもてなす祭儀を行うなど贈与することをポトラッチと呼び、権力証明に繋がる。年配の男性の性液を体内に摂取する成年儀礼が存在する。標準的な家族構成や婚姻ルールは国によって大きく異なる。旦那が亡くなったら旦那の兄弟と結ばれる、生物的父親と社会的父親が当たり前に分かれているケースもある。2025/10/05
swingswimmer
0
文化人類学の諸分野について、それぞれの著者のフィールドワークを交えながら概説する書籍。理論と具体的な事例がともに学べて面白かった。中でも6〜8章の儀礼や呪術、ひいては人間の世界の把握の仕方に関する理論や、9章の文化の伝播・継承方法とメディアとの関係(文化人類学そのものも写真や映像と不可分な学問であるところが興味深い)、11章の霊長類研究が面白かった。特にヒトとヒト以外の境界という位置づけがもたらす猿への畏怖や拒否という現象は、現在の人種間や文化間の様々な事象を考える手がかりになりうると感じた。2020/09/15
チェケ
0
個々のトピックに特化した部分は普遍性がないのであまり参考にならなかった面もあるが、象徴的解釈の禁忌との関連性、生成の語りと消滅の語りについての解説などはかなりためになった。2018/08/23
-
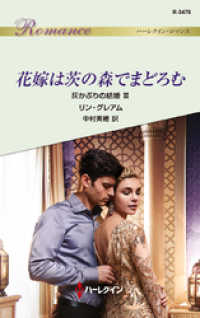
- 電子書籍
- 花嫁は茨の森でまどろむ ハーレクイン
-

- DVD
- ファースト・スピード