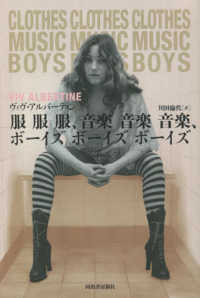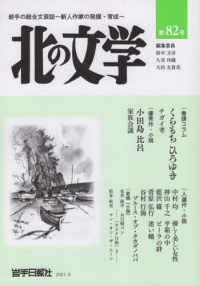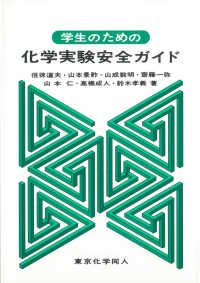出版社内容情報
堤 直規[ツツミナオキ]
内容説明
どんな部署でも必ず役立つ引継ぎ&仕事の作法!若手・中堅から、課長まで必読!
目次
1 内示が出た!焦らずしっかり異動に備える(そもそもなんで?公務員の頻繁な異動;意外と知らない?人事異動の手続き ほか)
2 最初が肝心!ここで差がつく最初の1週間(初日が大事!発令当日のポイント;さあ、引っ越し!初日から働こう ほか)
3 2か月勝負!業務を覚える、3年先を描く(最初の2か月が3年先の上限を決める;「首長目線」「上司目線」を意識する ほか)
4 手応え実感!地力を高める、実績を重ねる(能力と実績は経験年数に見合ってる?;2部署目!成果にこだわる、自省する ほか)
5 強みを磨く!異動を力に変える7つの習慣(担当業務でエースをめざす;「三芸」を修める、「弱み」を認める ほか)
著者等紹介
堤直規[ツツミナオタダ]
東京都小金井市企画財政部行政経営担当課長。東京学芸大学教育学部卒業、同大学院社会教育学専攻修了。東京学芸大学教育実践総合センター(当時)の技術補佐員(教育工学)を経て、2001年に小金井市役所に入所。行政管理課情報システム係、保険年金課、企画政策課、納税課を経て、2016年4月から現職。東京都市町村職員研修所「政策プレゼンテーション」研修内部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hatayan
37
現役の市役所職員が公務員の宿命である「異動」について前向きに考察。 異動を繰り返す中では厳しい人間関係や畑違いの仕事に直面することもある。しかし個人のキャリアの8割は偶然に起こる予期せぬ出来事で形作られるもの。逃げずに仕事に向き合うことで成果が生まれ、上司や同僚との絆が深まる。年数を経るごとに新人や若手と自分との距離は開いていくが、意識して職員の顔を覚え上下の世代をつなぐことで部署との間の関係が安定する。これまでの仕事の進め方を省みて、これからどうあるべきかを考えるための素材として目を通したい一冊です。2020/03/29
Ciel
23
異動については、毎年あるわけではないからなのかドキドキしてしまう。今の部署は正直一番行きたくないところでした。なので、発表になってから毎日憂鬱+異動後も憂鬱でした。でも、本書にも書いてある通り、ただ異動時期で今の部署の人も異動だったからチェンジしてみた、ではなく、何か意図があって(現在は段々明らかになってきている気がします)のものだったんだと納得できた。就職してからある程度経っているから事務処理できるのは当たり前。+αをどうしていかなければいけないかを考えないといけないと感じた。2019/11/28
ルーチェ
14
今の私の課題は引継ぎとマニュアルの作り方です。特に私の担当範囲ではマニュアルが無くて、聞いたり調べて身につけた物ばっかり。慣習的に口伝えが主なので、参考にするべきマニュアルが無いのです💦全仕事の書出し〜残務処理と引継ぎへの仕分け〜直接教える物と資料だけへの仕分け〜業務内容、予算、決算、懸念事項を書いていくという流れみたいです!大きな流れは分かりました!次は実際に使われるマニュアルはどんなの?という具体的な部分を調べてみたいです✨2019/01/05
yuki
12
公務員というわけではないけれど、参考になった。ある程度予想していたとおりこれを読んでいるときに本当に異動が決まり、前回の異動時もそうだったように寂しくなったり、細かいあれこれを考えたりして、他のことが手に付かない状態に。そんな自分にエールを頂いたような気持ち。最初の2か月が3年先の上限を決める。引継ぎを着任後すぐから作り始めるのはやはりいいことだったみたい。知識・技術・人脈か。異動先では一応また一年目でもあり、でも若手から中堅へ今後どうステップアップしていけばよいかが色々と書いてあって面白かった。2018/03/25
かばお
9
異動の準備にむけて、また読み直そう。また、異動・引継ぎのことだけじゃなくて、向上心をもって楽しく働くヒントも書かれている。いい本だけれど、この本から得た考え方をどうやって自分の業務に落とし込むか。2018/04/13