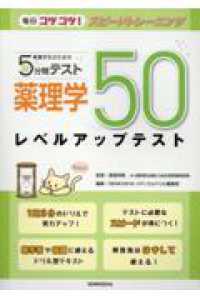内容説明
劇的な流動性、過剰ともいえる装飾性をもつ、ヨーロッパで栄えた美術・文化の様式「バロック芸術」。トロンプ・ルイユを駆使し、ロココが生まれた…。時代を画したバロックの建築・音楽・美術を総合的に論じる画期的な1冊。
目次
ヨーロッパの町角に今も息づくバロック
カトリックの改革とバロックの誕生―イエズス会の建築
リュベンスの建築と絵画
バロックの幕開け―サン・ピエトロ使徒座聖堂の拡張事業
歪んだ真珠―ベルニーニとボッロミーニ
バロック音楽の巨匠モンテヴェルディとサン・マルコ礼拝堂
イタリア・オペラとフランス・オペラ
フランスのローマ・バロック―ヴォー=ル=ヴィコント城館
ローマ・バロック敗れる―ルーヴル宮殿の拡張事業
王権のバロック―ヴェルサイユ宮殿
都市のバロック―ベラスケスの「ブレダの開城」
宮殿建築の建設ラッシュ―天井画の三大巨匠の一人ティエポロ
バロック建築の復活―パリの旧オペラ座
日本の町並みに息づくバロック
著者等紹介
中島智章[ナカシマトモアキ]
1970年福岡市生まれ。1993年東京大学工学部建築学科卒業。1998~2000年ベルギー・リエージュ大学留学。2001年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、博士(工学)。2001~2002年日本学術振興会特別研究員(PD)。2005年日本建築学会奨励賞受賞。現在、工学院大学工学部建築学科・准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mahiro
12
主に建築について写真を多く載せてバロックの成り立ち構造、ロココへの移行を解説している。ローマの建築も多く取り上げられ、ヴェルサイユやダルタニャン物語に出てくるフーケの館など失脚したため天井画が未完成な所とか興味深かった。又明治以降の日本の洋風建築にバロックがどのように取り入れられているかの説明もあった。京都国立博物館や東京国立博物館など今度行った時は見直してみたい。今年ローマに行って本書に載っている建物も幾つか廻ったのだが行く前に読めば良かったな。 2019/09/20
天々
6
荘厳さに溜息。無知ながらパリの旧オペラ座が粋の結晶・凝縮されているように思っていたけど、本書でもそのように紹介されていて嬉しい。2014/11/22
OKKO (o▽n)v 終活中
5
図書館 ◆ここに来てバロック建築とマニエリスム建築の境界線がわかんなくなってしまったため、基礎からやり直したい! ◆本書は建築、絵画、音楽など多様な側面からバロックを紹介する入門書2017/06/04
takao
2
ルネサンス芸術は均整な静的デザイン、バロック芸術は均整を破る動的デザイン。カトリック改革が芸術面で表出したもの。建築と彫刻と絵画が渾然一体。2017/01/24
takakomama
2
建築様式の細かい違いはよくわからないけれど、手の込んだ彫刻や絵画で飾られた建築物が素晴らしい。同じ時代なのに、音楽のバロックはずっと昔のようで、美術のバロックはそれほど昔に感じないのが、不思議です。 2016/05/14
-

- 洋書電子書籍
- Discussions on Chil…
-
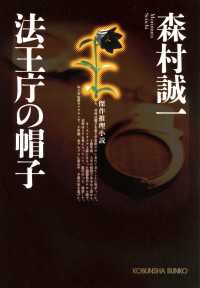
- 電子書籍
- 法王庁の帽子 - 傑作推理小説