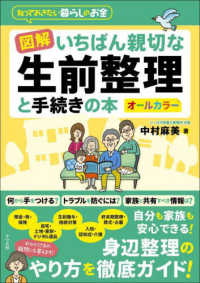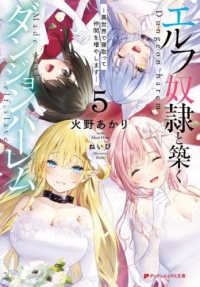内容説明
好奇心と冒険心に突き動かされ、男たちは船に乗った。その先に待つ苦難を乗り越え、アジアとヨーロッパをつなぎ、ダイナミックな世界図を描き出した。グローバルな視点に基づいた、新しい「大航海時代」論の決定版。
目次
第1部 未知なる東方へ―つながるヨーロッパとアジア(陸の道と海の路;地中海世界とインド洋;インド洋世界の発展;騎士・商人・伝道者)
第2部 大航海時代(ジェノヴァとポルトガル;コロンブスとインディアス;ポルトガルのアジア進出;香料諸島をめぐる争い;大航海時代と近代世界)
著者等紹介
増田義郎[マスダヨシオ]
1928年、東京生まれ。東京大学教授を経て東京大学名誉教授。専攻は文化人類学、イベリアおよびイベロアメリカ文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
大航海時代だけでなく、それに至るまでの世界の貿易の雄大な流れも丹念に描くことで「大航海時代」という西洋中心主義的な概念を相対化し、それだけでなくより適切にその意義と革新性も描いている。 鄭和の大航海を引くまでもなく、非西洋でもインド洋やアフリカまでまたがる貿易ネットワークは確立されていたし、むしろその歴史において、ヨーロッパはどちらかと言えば従属的な位置づけに過ぎない。 だが、大航海時代の冒険者達は自分たちの世界から飛び出た「全く新しい世界」を開拓する喜びと冒険者精神を謳歌できた。それが近代を準備したのだ2014/09/06
みなみ
11
新年から歴史の学び。大航海時代の本だけど、大航海時代以前の……それこそローマ時代からヨーロッパ世界がなにを求めていたのかから書いてある。ヨーロッパは貧しく、アジアは豊穣で、ヨーロッパ世界の欲しい嗜好品や高級な奢侈品がアジアにあった。十字軍の時代、モンゴルの脅威、イスラム勢力との戦い、オスマン帝国。それらを経てヨーロッパ世界は大西洋へと踏み出す。幾人もの冒険家がヨーロッパ人の知らない世界に到達した。コロンブスやマザランの航路も詳しく述べられとても勉強になる。でもまあこれが植民地支配に行っちゃうんだよなあ2026/01/02
ピオリーヌ
4
やっぱ概説書はさくさく読めていいなあ。改めて大航海時代の中での、1415年のポルトガルによるセウタ攻略の重要性を実感する。2018/09/22
ぱに
3
この著者が「大航海時代」の名付け親なのか!確かに英語で大航海時代って言わないもんなー。あと、結構この時代って、個人的には南米なイメージがあったけど、全然そんなことないってかむしろアジアが大事だった。ホント知識がなさすぎたので、時代の定義も知らなかったし(1492年頃からかと思ってた。1415まで遡るとは!)、ましてや終わりの時期なんて考えたことなかったな…。1648年か…。にしても初期のスペポル二強はすごすぎる。盛者必衰と悲しくなってしまった。2014/12/22
takao
2
ふむ2021/06/21
-
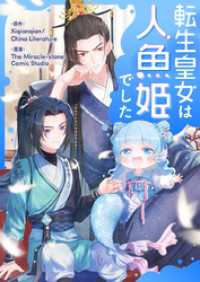
- 電子書籍
- 転生皇女は人魚姫でした【タテヨミ】第1…