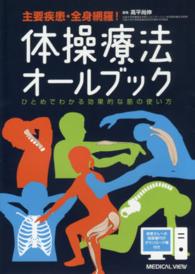内容説明
天下一の茶匠、千利休の全貌。桃山茶湯の大成者が求めつづけた世界とは何か。秀吉によって自刃を余儀なくされた悲運の芸術家の謎の生涯をドラマチックに追う。オールカラー、収録図版230余点。
目次
序章 室町文化と茶湯
1章 天文茶会記
2章 茶頭の時代
3章 城と山里
4章 利休の美意識
5章 利休をめぐる人びと
6章 死に至る道程
結章 利休の茶統
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大竹 粋
2
まずは図説で目でイメージをつかみたく、この本を手にしました。秀吉が何故利休を死に追いやったのか、謎なままですが、あの時代の茶の湯と政治がどのような関わりがあったのかとても興味深い話です。食から日本食への興味、日本食から魯山人へ、そして茶道へ、途中に青山二郎が入り、今ようやく利休から始めようというところです。すべては深い。 2014/07/14
takao
1
ふむ2021/08/30
jitchan
1
茶室は四畳半が主流だったのに利休は二畳の茶室を作り、「狭い、暗い」と秀吉の不興を買った。そんな話が今話題の『利休にたずねよ』に書かれていた。ところが本書を読むと、二畳の茶室は秀吉の発案だったというからへえっとなる。また、利休の死の責任を一方的に秀吉側に求める風潮があるが、平凡な茶碗に法外な値段をつけて私腹を肥やすなど利休側にも問題があった。さらに、秀吉が太閤になってからも、利休は私信の中で「秀公」と呼んで馬鹿にしていたという。秀吉の怒りを買うにはそれなりの理由があったのである【★★★★】2013/12/06
邪馬台国
0
利休関連5冊目。カラー図版は良いが、文章が堅くてなかなかとっつきにくいので、入門には不向きかも。利休関係の書籍を読めば読むほど、利休の聖人化を危険視する意見の多さに気づかされる。2015/03/13
-

- 電子書籍
- ルーガル2 ーZERODAYー【タテヨ…
-
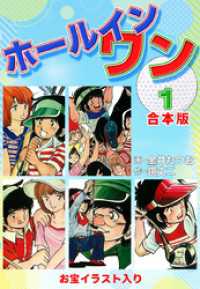
- 電子書籍
- ホールインワン(お宝イラスト入り)【合…
-
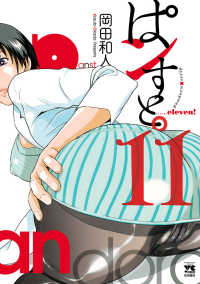
- 電子書籍
- ぱンすと。 11 ヤングチャンピオン・…
-

- 電子書籍
- 夫のためのやせごはん 我が家で活躍のヘ…