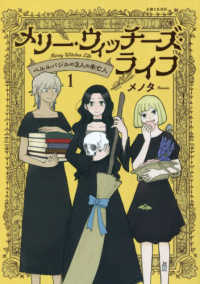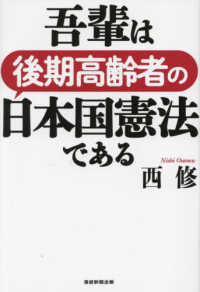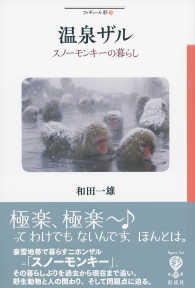出版社内容情報
【目次】
内容説明
「我々は誰なのか」「ロシアとは何なのか」―ソ連崩壊を契機として、ロシアのアイデンティティを問い直す思想潮流「ネオ・ユーラシア主義」が立ち現れた。ロシア・ウクライナ戦争の陰には、プーチンに強い霊感を与えたこのイデオロギーの存在がある…という見立ては正しいのか?ドゥーギンをはじめ、多様な論客が名を連ねる思想の実相とは?見取り図を第一人者が描出する。
目次
第一章 ネオ・ユーラシア主義誕生の背景(古典的ユーラシア主義;ユーラシア主義リヴァイヴァル ほか)
第二章 最右翼―アレクサンドル・ドゥーギン(ドゥーギンとは誰か;ドゥーギンのネオ・ユーラシア主義 ほか)
第三章 思想界のインフルエンサー―アレクサンドル・パナーリン(パナーリンとは誰か;パナーリンのネオ・ユーラシア主義)
第四章 主流化―実務家たち(アメリカへの対抗―イスラームとの共存;中国研究者たち―特にミハイル・チタレンコ ほか)
第五章 政界・思想潮流における現在地(ネオ・ユーラシア主義の共通項と伸縮性;ロシア・ウクライナ戦争のイデオロギー)
著者等紹介
浜由樹子[ハマユキコ]
東京都立大学法学部教授。津田塾大学大学院後期博士課程単位修得後退学、博士(国際関係学)。専門は国際政治学、国際関係史、ロシア地域研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
63
現代ロシアの思想というとドゥーギンくらいしか知らず、ヨーロッパ中心とした世界秩序に異を呈している。くらいしか知らなかったのだが、本書によってその蒙を啓かれた。在野のドゥーギンとアカデミズムで活躍したパナーリンの二人を軸にロシア革命期に成立したユーラシア主義という思想とそれが現代ロシアにどのような影響を与えているかを明らかにした名著。読んでいるとロシア人の心底にはソ連崩壊後の90年代のトラウマとヨーロッパに対する二律背反的な感情が未だ強く残っているのを教えられるなあ。戦争が肯定されるわけじゃないけど。2025/08/01
紙狸
22
2025年6月刊行。ロシア・ウクライナ戦争が長期化する中、ロシアの思想を対象とする研究が、一般読者に向けた良書を生み出した。著者によれば、ネオ・ユーラシア主義が、戦争に直結した訳ではない。ネオ・ユーラシア主義を論じることは、ロシアの思想状況を理解する補助線をひくことだ。具体的思想家としてドゥーギンを最初に置いたのは世間の関心に応じたもので、著者は次章に置いたパナーリンという政治思想研究者(故人)をより高く評価しているようだ。パナーリンの議論を読んで、紙狸としては、佐伯啓思氏の所論を想起した。2025/08/12
無重力蜜柑
14
良著。「ユーラシア」はソ連崩壊後のロシアのアイデンティティを規定する概念だ。それはヨーロッパでありアジアでもある(あるいはどちらでもない)ロシアという意味内容を持ち、大抵は西欧や米国への政治的、経済的、理念的対抗関係を念頭に置いている。この発想は大戦間期の亡命ロシア人の思想(古典的ユーラシア主義)に淵源し、ソ連では政治的統制のもとで忘却されていたそれが新生ロシアで復活したのがネオ・ユーラシア主義である。ウクライナ侵攻以後は、プーチン政権の右翼イデオロギーの基盤として西側ではしばし言及される。2025/07/02
スプリント
8
ドゥーギンはウクライナ関連のテロで娘さんを亡くした事件で名前を知っていた。ネオ・ユーラシア主義の大家。 あとはパナーリン。 ネオ・ユーラシアは地政学的にみると不凍港がそのエリアにほぼ存在しないのでヨーロッパはアメリカ、南米などに比べると経済圏の中心にはなりづらいと思う。2025/08/26
かずい
4
現在ロシアは欧州かアジアでもないユーラシアであるとするかつてのユーラシア主義からポスト冷戦を経てネオユーラシア主義が広がっている。反欧米、反リベラリズム、ロシア中心主義を掲げ、思想家としてドゥーギンやパナーリンが主体となっている。背景にソ連崩壊後の混乱で欧米にやられたという被害意識が強く残っているという。プーチンの初期は全方位外交でユーラシア主義者からは批判されていたらしい。ネオユーラシアリズムはプーチンの変化、ウクライナ侵攻なども、欧米で起きた反グローバリズムの潮流の一環のような気がしてきた。2025/10/19
-

- 電子書籍
- 元農大女子には悪役令嬢はムリです!【タ…
-
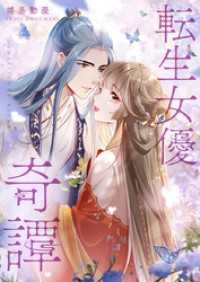
- 電子書籍
- 転生女優奇譚【タテヨミ】第72話 pi…