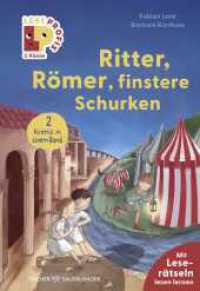内容説明
世界に一大ネットワークをつくる―権力者もできなかった、この偉業をなしとげたのは彼らだった!メソポタミア商人、フェニキア人、ハンザ商人、大航海時代からタックスヘイブンまで、11の商人を通して俯瞰する、交易と覇権の歴史。
目次
第1章 メソポタミアの商人―世界で最初の商人
第2章 フェニキア人―地中海商業の覇者
第3章 パルティアの商人―シルクロードで大儲けしたローマ帝国のライバル
第4章 イスラーム商人たち―コーランと商売
第5章 ソグド商人―シルクロードの立役者
第6章 イタリア商人・セファルディム・アルメニア商人―地中海から世界へ
第7章 ヴァイキング・ハンザ商人・オランダ商人―北の海の遺伝子
第8章 ポルトガルとスペイン―大航海時代の運び屋たち
第9章 中間商人としての大英帝国―運び屋から手数料ビジネスへ
第10章 領事から総合商社へ―日本経済の発展を支えた組織
第11章 大英帝国・タックスヘイブン・IT企業―中抜きされる社会
著者等紹介
玉木俊明[タマキトシアキ]
1964年生まれ。現在、京都産業大学経済学部教授。専門は近代ヨーロッパ経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ta_chanko
21
世界史=交易の歴史。太古の時代から、人々はより豊かな生活を目指して、遠隔地との交易をおこなってきた。戦争によって版図の拡大を図るのも、市場を拡大し交易の安全を実現するため。商業覇権を握ってきたのは、フェニキア・ギリシャ・ローマ・イスラーム・イタリア・ポルトガル・スペイン・オランダ・イギリス・アメリカ。その間、アルメニア人・ノルマン人・セファルディム(ユダヤ人)なども国や地域を横断して活動し、世界の交易に重要な役割を担った。産業革命後は、電信の使用手数料・保険料などでの利益が大きくなり商業の金融化が進行。2023/10/21
feodor
9
古代文明の段階から、生産地と生産地を結びつける「中間商人」の存在があり、交易が成立した、という話。ヨーロッパでの交易を担当したのが、イタリア商人だけでなく、セファルディムとアルメニア商人であった、というのは初知り。大航海時代を迎え世界交易に、グローバル化を一挙に成し遂げたのがポルトガルとスペイン。そして、それに代わる存在となった大英帝国は、航海法などにより最初は輸送手段を独占し、さらに電信という通信手段によって使用料ビジネスを始める。また、現代の中間証人はIT産業である、とも。なかなかおもしろかった。2023/10/16
さぶろうの領土
7
ドラクエで戦士や魔法使いに交じり【商人】という職業がいるのを見た時に思った。商人だけ浮いてるよな、と。ちょっと一枚落ちるよな、と。しかしよく考えてみると現実の歴史において商人以上に、世界各地で縦横無人に旅・冒険をした人たちはいないのではないだろうか。現代では想像できないほどに各コミュニティー間に隔たりがあり、危険だったに違いない。それこそ強い意志と勇気が必要だっただろう。彼らの類稀な勇気により世界は徐々につながりを持って行ったのだ。2023/12/30
seu
3
商品の生産の面ではなく、モノとモノ、ヒトとヒトを媒介する「中間商人」に着目した一種のテーマ史。フェニキア人、パルティア商人、ソグド商人など、異なる文明間でモノや情報の交換、さらには文化の伝播に寄与した歴史上の中間商人を取り上げ、その歴史的意義について簡潔に解説。2024/10/15
6
3
○メソポタミア文明、シュメール人、塩害。フェニキア人・カルタゴからローマへ。シルクロードの中間商人・パルティア人。モンゴル帝国の財務官僚・イスラーム教徒。ソグド商人、唐からビザンツへ。セファルディム(ユダヤ人)、インド(ダイヤモンド)と新世界(砂糖)。ヴァイキング、交易と掠奪。イギリス、海運とインフラ(鉄道、電信)、電信によるコミッション→金融業の発達。領事と総合商社、情報収集。タックスヘイブン、王室属領、国王が統治するが国には属さない。ITという中間商人に気づかぬうちにコミッションを取られる2023/11/09